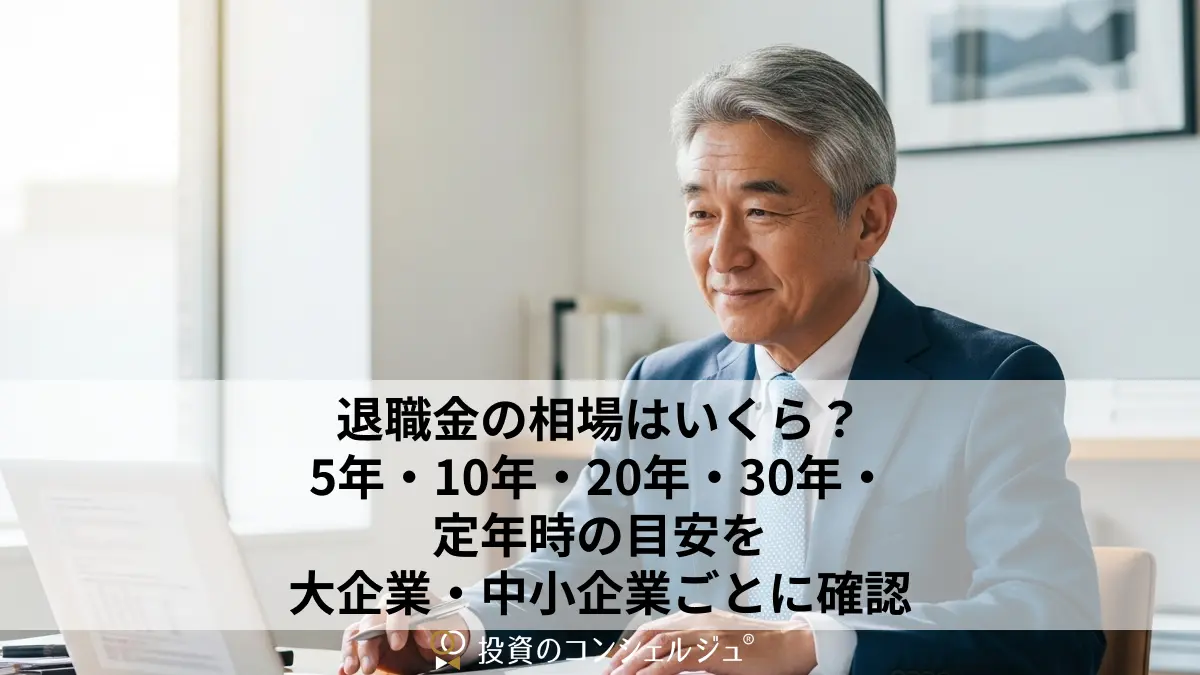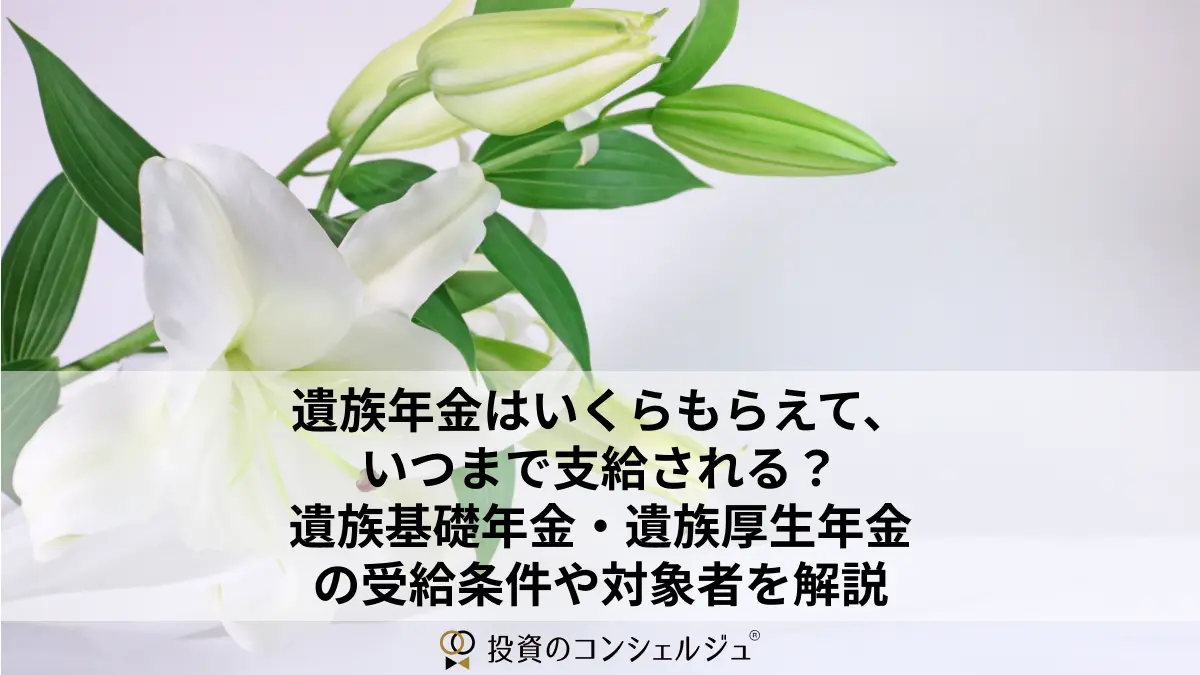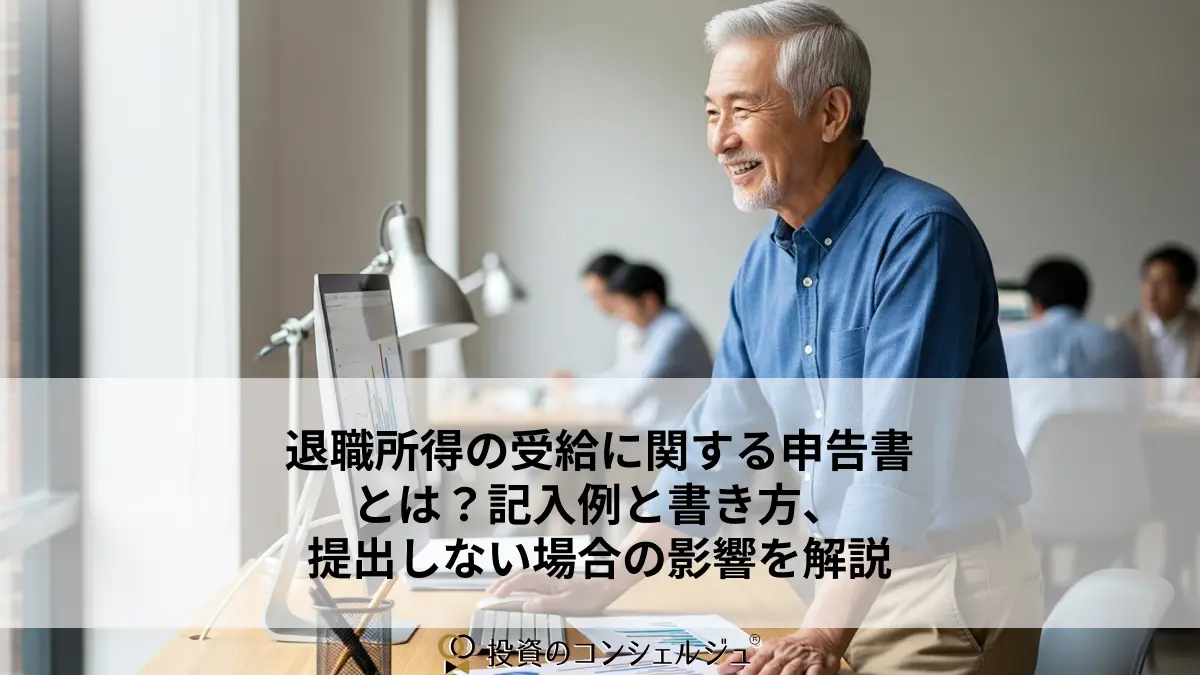退職金の税金はいくら?退職所得控除の計算方法や具体例、損しないための「5年ルール」「19年ルール」などを解説
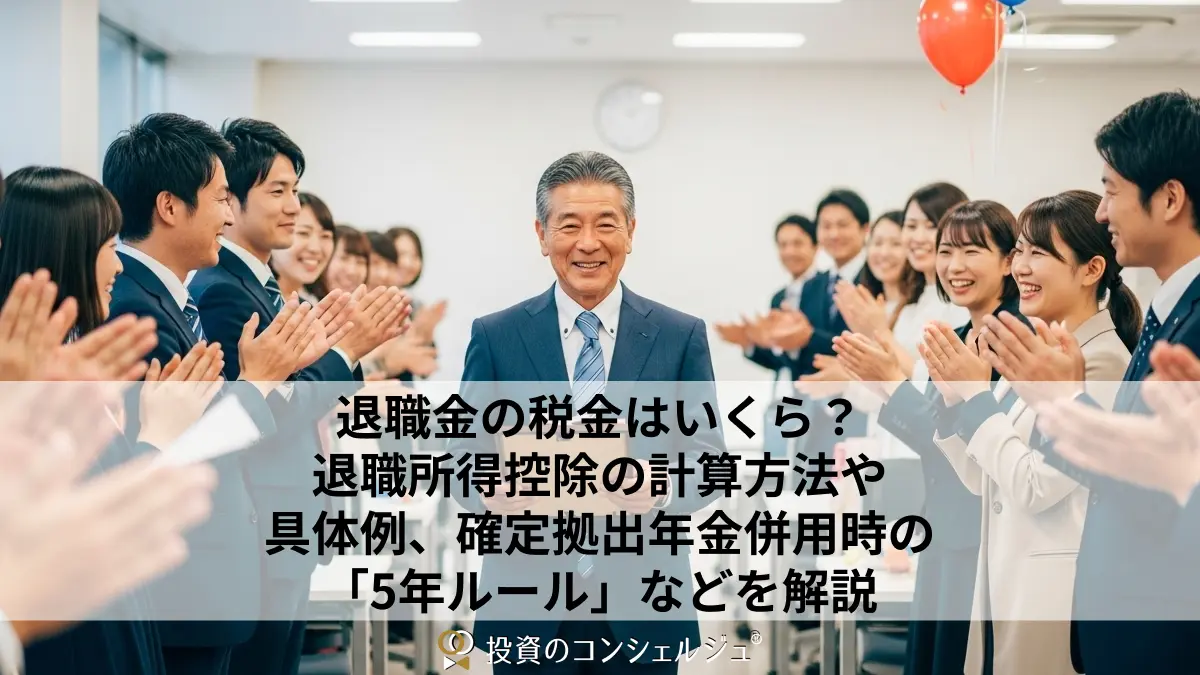
退職金の税金はいくら?退職所得控除の計算方法や具体例、損しないための「5年ルール」「19年ルール」などを解説
難易度:
執筆者:
公開:
2024.07.26
更新:
2025.12.17
退職金とiDeCo・企業型DCの一時金は、受け取り方やタイミング次第で「退職所得控除」の効き方が変わり、税額が想定より増減することがあります。とくに複数回受給では、5年・10年・19年ルールや控除の重複調整を誤解すると、後から「順番を変えればよかった」となりがちです。この記事では、退職所得控除の基本から年数ルールの考え方、計算例・シミュレーション手順まで整理し、自分に合う受給計画と概算税額の見通しを作れるように解説します。
サクッとわかる!簡単要約
退職金とiDeCo・企業型DC一時金を同時期に受け取ると、退職所得控除が重複調整されて税額が変わる仕組みを、5年・10年・19年ルールを軸に理解できます。勤続年数の数え方から控除額と課税退職所得の計算、よくある誤解まで整理し、受給順序や受給時期を自分で設計して概算税額の見通しを立てられるようになります。
目次
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出にすれば源泉徴収され確定申告は不要
1. 通常のケース:「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出
2. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は確定申告が必要
退職金を複数回受け取る場合の注意:「5年ルール」と「19年ルール」
確定拠出年金の一時金に適用される退職所得控除の19年ルールと注意点
複数箇所に勤務しており、3年違いで退職し退職手当を受け取り5年ルールが適用されてしまう場合
iDeCoを一時金として受け取り、2年後に企業からの退職金も支給され、5年ルールが適用されてしまう場合
早期退職により、iDeCoを一時金で受け取れる60歳より前に退職金が支給されてしまい、19年ルールが適用されてしまう場合
退職金の税金はどう決まる?
退職金は長年の勤労に対する報償的な性格を持つため、他の所得と比べて税制上優遇されています。退職金を受け取る際には、所得税と住民税の2種類の税金が課税されます。
かかる税金は所得税・住民税
退職金にかかる所得税は、退職所得として分離課税の対象です。まず退職金の金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1が課税対象となります。
退職金にかかる住民税も、所得税と同様に分離課税方式が採用されています。課税対象額の計算方法は所得税と同じで、退職金から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1に対して課税されます。税率は一律10パーセントで、都道府県民税が4パーセント、市区町村民税が6パーセントという内訳です。
勤続年数・加入期間の数え方
退職所得控除の計算で最初に確定すべきなのが「勤続年数(会社退職金)」と「加入期間(iDeCo・企業型DCの一時金)」です。ここが1年ズレるだけで控除額が変わります。
- 退職所得控除は勤続年数に連動して増えます。勤続年数は原則として「退職の日まで引き続き勤務した期間の年数」で、1年未満の端数があれば1年に切り上げます。
たとえば会社の退職金で、勤続期間が「10年2か月」なら、勤続年数は端数切り上げで「11年」として扱います。なお、退職所得控除についてはは以下もご参照ください。
退職金にかかる税金を計算するときの流れ
具体的に、退職金を受け取ったときに発生する税金の計算方法について見ていきましょう。
ステップ1:退職所得控除を計算する
退職所得控除とは、退職金など退職所得の総収入額から差し引くことができる控除額のことです。勤続年数に応じた一定額が控除され、その後で税額計算が行われます。勤続年数が長いほど控除額は大きく設定されており、長年勤務した人ほど税負担が軽減される仕組みです。
勤続年数の数え方は、在職期間の通算年数を基本とし、月数の端数がある場合は切り上げて1年とします。例えば、勤続20年6か月なら21年とみなします。
退職所得控除額の基本的な計算式は次のとおりです。
退職所得控除の計算式
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(ただし、最低控除額は80万円)
- 勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
まず勤続年数が20年以内なら年40万円ずつ控除でき、たとえ勤続年数が2年や1年の場合でも最低80万円は控除可能です。勤続年数が20年を超えると、20年分として一律800万円に加え、21年目以降は1年あたり70万円ずつ控除額が増えます。
例えば、勤続年数が5年の場合、退職所得控除額は以下のように計算されます。
退職所得控除の計算例
- 勤続5年の場合:40万円×5年=200万円
- 勤続37年の場合:800万円+70万円×(37年-20年)=1,990万円
この計算式から分かるように、勤続年数が長くなればなるほど、退職所得控除額は大きくなります。その結果、退職所得の金額が小さくなり、税負担も軽減されることになります。
ステップ2:退職所得控除に1/2を乗じる
退職所得控除を差し引いた後の課税対象額(課税退職所得金額)は、その半分だけが所得税・住民税の課税対象になります。計算式で表すと、通常の退職所得については次のようになります。
- 課税退職所得金額=(退職金などの総収入金額-退職所得控除額)×1/2
ステップ3:所得税率表に当てはめて退職所得の税額を計算する
上記で求めた課税退職所得金額に対し、所得税は超過累進税率(いわゆる所得税の税率表)に従って計算されます。退職所得は他の所得と分離して課税されますが、税率自体は通常の所得税率と同じ体系です。以下に所得税の速算表に基づく税率と控除額を示します(所得税は課税退職所得金額にこの税率を当てはめ、算出税額から控除額を引いて計算します)。
| 課税退職所得金額(課税対象額) | 所得税率 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,329,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,330,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税に加えて、課税所得金額に対して住民税10%(一律)も課税されます。また算出された所得税額の2.1%にあたる復興特別所得税も別途かかります。住民税と復興特別所得税は課税退職所得金額に直接定率を乗じて計算します(住民税には控除額はありません)。
実際に退職金にかかる税金をシミュレーション
実際に、退職金にかかる税金がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
条件
- 退職金:2,200万円
- 勤続年数:37年の場合
- 退職所得控除額:1,990万円
この場合、退職所得は以下のように計算されます。
- 退職所得:(2,200万円-1,990万円)×1/2=105万円
この退職所得105万円に対して所得税・復興特別所得税および住民税が課税されます。
所得税は、課税退職所得金額(105万円)に税率(5%)をかけ、控除額(0円)を差し引いて計算されます。復興特別所得税は所得税額×2.1%、住民税は、課税退職所得金額に定率10%で計算されます。
退職所得105万円の場合の税額
- 所得税:105万円×5%-0円=52,500円
- 復興特別所得税:52,500円×2.1%=1,102円(端数切り捨て)
- 住民税:105万円×10%=105,000円
- 税の総額:158,602円
退職金2,200万円から税額158,602円を引いた金額が、手取り額となり、21,841,398円(約2,184万円)です。退職金が2,200万円の額面でも、手取りが2,184万円とかなり大きく、受給者に優位な制度設計になっていることがわかります。
なお、退職金の相場は勤続年数や企業の規模によっても異なります。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
退職金より退職所得控除額が多い場合は税金がかからない
「受け取る退職金≦退職所得控除」の場合、退職金に税金はかかりません。具体的な例を見てみましょう。
条件
- 勤続年数:10年
- 退職所得控除額:40万円×10年=400万円
- 退職金:300万円
この場合、受け取った退職金300万円は控除額400万円より少ないため、課税対象となる所得はゼロです。つまり、退職金に対して税金はまったくかかりません。
退職金の額が退職所得控除の範囲内に収まっていれば、そのまま全額を受け取れます。会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、確定申告も不要です。
退職金をもらった翌年の税金に関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出にすれば源泉徴収され確定申告は不要
一般的に会社員が退職する際、退職時の税金処理は、原則として会社が行いますが、状況によっては自分で確定申告が必要な場合があります。
1. 通常のケース:「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出
退職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、会社で所得税と復興特別所得税を計算し、源泉徴収します。この場合、通常は確定申告の必要はありません。
ただし、退職金と関係なく確定申告を行う場合(医療費控除・寄附金控除等の申請や雑所得が年間20万円以上の場合など)は、確定申告書に退職所得を記載する必要があります。いずれにせよ、「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば退職金に起因して確定申告を行う必要はありません。
2. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は確定申告が必要
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から一律20.42%の税金が源泉徴収されます。この場合は、後日確定申告により、税額を調整を行うことができます。税率が20.42%を下回る場合は還付金が受け取れます。
一方、税率が20.42%を上回っていた場合、無申告加算税や延滞税が加算されるなどペナルティが発生する可能性があります。十分注意し、確実に確定申告をおこなうようにしましょう。
税額を正確に把握するためには、会社に任せきることなく、事前にご自身でも計算することをおすすめします。これは退職後の生活の準備にも役立ちます。
「退職所得の受給に関する申告書」の書き方は、退職日よりも前に提出する必要があります。詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
退職金を複数回受け取る場合の注意:「5年ルール」と「19年ルール」
退職所得控除には「5年ルール」と「19年ルール」と呼ばれる取り決めがあります。これは複数回に退職金(一時金)を受け取る場合に、受け取りの間隔によって退職所得控除が大きく減額されてしまう仕組みです。通常の会社からの退職手当等には5年ルールが適用され、企業型DCやiDeCoなど確定拠出年金の一時金には19年ルールが適用されます。
簡単に言えば、前に受け取った退職金との間隔が短いと控除の重複が認められず、その分課税対象が増えてしまうのです。以下でそれぞれのルールについて説明します。
受取タイミングによる退職金の節税戦略については以下でも説明しています。
退職所得控除の「5年ルール」とは
退職所得控除の5年ルールとは、ある退職金を受け取った年(以下、前回)から5年以上間隔をあけずに次の退職金を受け取ると、退職所得控除が満額使えなくなる仕組みです。

「前回受け取り年の翌年から起算して4年以内」に他の退職金を受け取った場合、勤続期間が重複する部分の控除が受けられなくなるのです。
例えば2035年に退職金を受け取った場合、次に満額の退職所得控除を受けられるのは2040年以降となります。2039年まで(2039年含む)に別の退職金を受け取ってしまうと5年ルールに抵触し、控除額が減額されます。言い換えると前回の退職金受取から5年以上間隔を空ける必要があるため、この規定が「5年ルール」と呼ばれます。

退職金を複数回受け取る場合、受取時期が近いと(5年未満だと)退職所得控除が減額されて手取りが減ることに注意しましょう。可能であれば、退職金の受け取りは5年以上間隔を空けることが望ましいです。
2026年から「5年ルール」は「10年ルール」に
2025年度の税制改正(令和7年度改正)で退職金とiDeCo/DC一時金の受取間隔がこれまでの約5年から約10年に延長されました。
具体的には、「退職手当(退職金)を受ける年の前年以前9年以内」にDC一時金を受け取っていた場合、勤続年数の重複排除による控除調整の対象となるよう改められます(改正前は「前年以前4年以内」)。これを平易に言い換えると、iDeCoや企業型DCの一時金を先に受け取った場合、その後10年以上間隔を空けないと、後から受け取る退職金で退職所得控除を満額利用できなくなるということです。
従来は5年空ければセーフだったものが、改正後は倍の10年空けないと同じ恩恵を受けられません。 この改正は2026年1月1日以降に支払われるDC一時金と、それに続いて受け取る退職金から適用される予定です。つまり、2025年末までに受け取る給付については旧ルールが適用され、それ以降は新ルールに切り替わります。
なお、「5年ルール」と「10年ルール」の違いに関しては、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
確定拠出年金の一時金に適用される退職所得控除の19年ルールと注意点
退職所得控除の19年ルールとは、企業型DCや個人型DC(iDeCo)など確定拠出年金の一時金に対して適用される特例です。具体的には、確定拠出年金の一時金を受け取る場合に、その受取前年以前19年以内に他の退職金を受け取っていた場合、重複する勤続(加入)期間分の退職所得控除が受けられないという仕組みです。通常の会社退職金とは異なり、この19年ルールは確定拠出年金にのみ適用されます。

例えば、会社からの退職金を受け取った後19年以内にiDeCoの一時金を受け取るような場合が該当します。前述の5年ルールよりも長期間にわたって控除の重複が制限される点が大きな違いです。言い換えれば、前回の退職金受取から20年以上(=19年超)経過していれば確定拠出年金の一時金にも退職所得控除を満額適用できますが、それ未満の間隔だと一部控除が受けられません。

このため「企業型DCやiDeCoを受け取ってから5年後以降に、次の退職金受取をしたほうがいい」と言われます。
- 特に早期退職して企業から退職金をもらい、その後数年以内にiDeCoの一時金も受け取るようなケースでは、19年ルールによりiDeCo側の控除が大幅に削られてしまうため注意が必要です。
確定拠出年金を一時金で受け取る場合の注意点は以下もご参照ください。
退職所得控除が減額されてしまう受け取り方の例
以下では、5年ルール、19年ルールの適用でどのように退職所得控除や退職所得が変化するかの例を示します。受け取りのタイミング調整が難しい退職手当でない限り、5年ルール・19年ルールの適用されないタイミングでの受け取りが税額を少なく、手取り額を大きくできます。
複数箇所に勤務しており、3年違いで退職し退職手当を受け取り5年ルールが適用されてしまう場合
45歳から65歳まで20年間A社に、58歳から68歳までB社にそれぞれダブルワークで勤務し、A社から2000万円、B社から1000万円の退職金が支給された場合を考えます。
65歳のとき、A社から受け取る退職金の退職所得控除と退職所得は以下の通りです。
A社から受け取る退職金の控除と所得
- 退職所得控除:40万円/年×20年=800万円
- 退職所得:(2,000万円-800万円)÷2=600万円
68歳の時にB社から受け取る退職金への退職所得は、4年以内にA社からの退職金を受け取っているため、重複期間分の退職所得控除が得られません。重複していない66歳から68歳の3年間のみ計上されます。
B社から受け取る退職金の控除と所得
- 退職所得控除:40万円×3年=120万円
- 退職所得:(1000万円-120万円)÷2=440万円
B社退職金に退職所得控除が満額受けられていた場合
- 退職所得控除:40万円×10年=400万円
- 退職所得:(1000万円-400万円)÷2=300万円
5年ルールが適用されたことにより、140万円の課税所得がプラスされてしまいました。このように、複数の退職金を受け取る場合、受け取る時期が近いと退職所得控除が減額され、税額が大きくなってしまいます。
早期退職した時の退職金に関する税金は、こちらのQ&Aも参考にしてみてください。
iDeCoを一時金として受け取り、2年後に企業からの退職金も支給され、5年ルールが適用されてしまう場合
例えば、iDeCoに50歳から加入している人が、63歳の時に一時金として500万円の受け取りを行い、65歳の時に25歳から40年間勤めた企業の退職金2,000万円を受け取る場合の事を考えます。
63歳で受け取るiDeCo一時金に対する退職所得控除は、加入期間13年のため、40万円/年×13年=520万円となります。一時金の500万円よりも額が大きいため、非課税です。
65歳で受け取る退職金に対する退職所得控除は、勤続40年からiDeCoとの重複期間13年が削られ、27年分となります。
<企業の退職金の控除と所得>
- 退職所得控除:800万円+70万円/年×7年=1,290万円
- 退職所得:(2,000万円-1,290万円)÷2=355万円
<企業退職金の控除が満額だった場合>
- 退職所得控除:800万円+70万円/年×(40年-20年)=2,200万円
- 退職所得:0円(非課税)
退職金を受け取る4年以内に、別の退職金であるiDeCoの一時金を受け取ってしまったため、退職所得控除が減額されてしまいました。この場合だと、iDeCoの一時金を60歳の時に受け取っていれば、65歳で受け取る企業からの退職金も満額退職所得控除の対象でした。このように受け取りのタイミングは非常に重要です。
早期退職により、iDeCoを一時金で受け取れる60歳より前に退職金が支給されてしまい、19年ルールが適用されてしまう場合
22歳から35年間務めた会社を57歳のときに退職し、退職金を受け取った人が40歳からiDeCoも加入していた場合を考えます。早期退職により57歳で退職金が支給されてしまうと19年ルールにより、iDeCoの退職所得控除が満額受けられるのは57歳から19年後の76歳のとき、ということになります。
iDeCoを一時金として受け取れるのは75歳までなので、iDeCoを一時金で受け取ろうとしても退職所得控除が大きく削られ、税額が大きくなってしまいます。具体的に数字を置いてみると以下のようになります。
退職金が22歳から勤続35年、57歳の時に2,000万円だった場合として計算します。
<企業からの退職金にかかる控除と所得>
- 退職所得控除:800万円+70万円/年×15年=1,850万円
- 退職所得:(2,000万円-1,850万円)÷2=75万円
一方、iDeCoが40歳から65歳まで積立てを実施し、65歳で一時金を500万円受け取る場合は次のようになります。
<19年ルールにより重複期間の退職所得控除が減額された場合>
- 退職所得控除:40万円/年×(加入期間25年-重複期間17年)=320万円
- 退職所得:(500万円-320万円)÷2=90万円
<iDeCoに対する退職所得控除が満額の場合>
- 退職所得控除:800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
- 退職所得:0円(非課税)
このように、受け取る順番や感覚によって税額が大きく異なることがおわかりいただけたかと思います。
退職金の受け取り方による受取金額の違いについては以下の記事でも詳しく説明しています。
勤続5年以下の場合の退職所得課税(短期退職手当等)
勤続年数が5年以下と短い場合、退職金などの所得は税法上「短期退職手当等」とみなされ、課税方法が少し異なります。特定役員以外の一般社員について、勤続5年以下の退職手当等に対する退職所得の計算は、退職所得控除後の金額が300万円を超えるか否かで扱いが分かれます。
退職所得控除後の金額が300万円以下の場合
通常の退職所得と同様に、控除後の残額の1/2が課税退職所得金額になります。つまり 「(退職金総額 - 退職所得控除額) ÷ 2」 で計算します。
退職所得控除後の金額が300万円を超える場合
短期退職手当等の場合は、300万円を超える部分について税負担が重くなります。具体的には、その超過分は半分ではなく全額が課税対象となる計算式に置き換わります。
- 課税退職所得=150万円+{退職金総額-(退職所得控除額+300万円)}
ここで150万円というのは、300万円までの部分を通常通り1/2した金額(=150万円)を意味しています。
短期退職手当等の例
例として、勤続4年で退職金600万円を受け取ったケースを考えます。退職所得控除の金額と、控除後の金額は以下のとおりです。
<短期退職手当等の場合の退職所得控除と退職所得>
- 退職所得控除額:40万円×4年=160万円
- 退職所得:600万円-160万円=440万円
これは300万円を超えているため特例計算が適用され、課税退職所得金額は以下のようになります。
- 課税退職所得金額=150万円+(600万円-(160万円+300万円))=290万円
一方、もし通常計算(半分課税)であれば以下のとおりです。
- 課税退職所得金額=(600万円-160万円)÷2=220万円
短期退職手当等の特例により、このケースでは課税対象額が70万円増えていることがわかります。つまり、勤続5年以下で退職金の金額が大きい場合は、一定額を超えた部分について税金が重くかかる仕組みになっています。短期勤続で退職金を受け取る際は、この計算方法の違いに注意しましょう。
5年以下の役員・議員・公務員の期間がある場合の退職所得控除の特例
勤続期間のうち5年以下の期間を役員等として勤務していた場合、その期間に対応する退職金については別途「特定役員退職所得控除額」という計算方法が適用されます。役員や議員、公務員としての勤続が短期であるケースでは、退職所得控除の扱いと課税方法が一般とは異なり、その分税負担が重くなる点に注意が必要です。
「特定役員」に該当するのは次の3種類のような立場の人を指します。

- 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
- 国会議員および地方公共団体の議会の議員
- 国家公務員および地方公務員
要するに会社役員や議員などが在任5年以内で退職した場合に該当し、その役員等期間に対応する退職金については課税が厳しくなります。具体的には、通常の退職所得控除額は勤続年数に応じて計算しますが、役員等として5年以下勤務した部分の退職金については、退職所得控除後の金額を2分の1にする優遇措置が適用されません。
特定役員退職所得控除額の例
例えば、ある人が15年間勤めた会社の最後の4年間を執行役員として過ごし、一般社員としての11年分の退職金1,100万円と、執行役員としての4年分の退職金600万円を受け取ったとします。この場合、退職所得控除額は以下のように計算されます。
一般社員と執行役員がある場合の退職所得
- 一般社員分:(1,100万円-(40万円/年×11年))÷2=330万円
- 執行役員分:600万円-(40万円/年×4年)=440万円
- 退職所得金額の合計:330万円+440万円=770万円
特定役員退職所得については、一般の退職所得控除のように課税退職所得金額を2で割ることはありません。そのため、課税退職所得金額が一般の場合と比べて大きくなります。
この例の場合、所得税額は「課税退職所得金額770万円×税率23%-控除額636,000円=所得税額1,135,000円」と計算できます。
住民税は77万円、復興特別所得税は23,835円となることから、退職金の手取り金額は、15,071,165円(約1,507万円)です。
このように、特定役員退職所得控除額の計算方法は一般の退職所得控除とは異なり、特定役員としての勤務期間が5年以下の場合、その部分の退職金に対しては税負担が重くなる点に注意が必要です。
この記事のまとめ
退職金とiDeCo・企業型DC一時金は、受給の順番や間隔によって退職所得控除の効き方が変わり、税額が想定より増えることがあります。5年・10年・19年ルールや重複期間の考え方を押さえれば、控除を無駄なく使う受給計画を立てられます。
次は、退職金見込額・iDeCo/DC残高・加入期間(勤続年数)と受給予定日を並べ、記事の手順で概算税額を試算しましょう。判断に迷う場合は、勤務先や金融機関、税理士への相談も有効です。投資のコンシェルジュでも、退職金の宇受取方法や老後資産に関する無料相談を行っています。お気軽にご利用ください。

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連する専門用語
確定給付年金
確定給付年金(Defined Benefit)とは、受給者の給与や勤務年数などによってあらかじめもらえる金額が決まっている年金のこと。給付額が制度資産の利回りに依拠しないという特徴がある。確定給付企業年金を指す言葉として用いられることもある。受給者に対するメリットとしては、確定給付年金(DB)は確定拠出年金(DC)と比べて資産管理に気を使わなくてよく、老後の安定的な収入源になるが、償却負担が重い場合には給料に悪影響を及ぼす可能性があり、受給権がわかりにくいというデメリットがある。
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。
確定拠出年金(DC)
確定拠出年金(DC)は、毎月いくら掛金を拠出するかをあらかじめ決め、その掛金を自分で運用して増やし、将来の受取額が運用成績によって変わる年金制度です。会社が導入する企業型と、自分で加入する個人型(iDeCo)の二つがあり、掛金は所得控除の対象になるため節税効果があります。 運用対象は投資信託や定期預金などから選べ、運用益も非課税で再投資される仕組みです。60歳以降に年金や一時金として受け取れますが、途中で自由に引き出せない点に注意が必要です。老後資金を自ら準備し、運用の成果を自分の年金額として受け取る「自助努力型」の代表的な制度となっています。
住民税
住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。
分離課税
分離課税(ぶんりかぜい)とは、特定の所得について他の所得と合算せず、その所得単独で税額を計算し、課税する方式です。分離課税には「源泉分離課税」と「申告分離課税」の2種類があります。
総合課税
総合課税は、給与や年金、事業収入、不動産収入、利子、配当など、1年間に得たさまざまな所得を合算し、その合計額に累進税率を適用して所得税を計算する方式です。 所得が増えるほど税率が高くなるため、高所得者ほど税負担が大きくなる点が特徴です。一方、金融所得には総合課税以外の課税方法を選択できる場合があります。 たとえば、株式譲渡益や先物取引益などは「申告分離課税」を選ぶことで、ほかの所得と区分して一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で申告できます。 また、預貯金利息や一部の公社債利子などは、支払元が税金を源泉徴収する「源泉分離課税」となり、原則として確定申告は不要です。配当や利子のように課税方式を選択できるケースでは、ご自身の所得水準や控除の有無、損益通算の可能性を踏まえ、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税のどれを採用するかを検討することが、最終的な税負担を抑えるうえで重要になります。