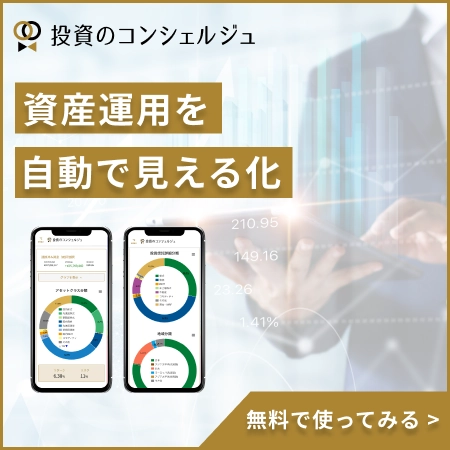中退共で充実した退職金制度を確立!基本内容とメリット、デメリットを徹底解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.02
更新:
2025.04.02
中小企業でも導入しやすく、従業員の定着や節税にもつながる退職金制度、それが「中退共」です。「うちの規模でも本当にできるのか?」と不安な経営者に向けて、この記事では導入ステップから制度の仕組み、税制メリットまでをわかりやすく解説します。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むことで、「中退共って結局どう使えるの?」という疑問が解消されます。制度の基本から、他制度(確定給付年金など)との違い、掛金設定の具体例、さらには導入時の助成金まで、実務に即した情報が網羅されています。特に中小企業が抱えやすい「資金繰り」や「事務手続きの負担」に対して、中退共ならどう軽減できるかが具体的にわかるため、「明日から準備できそう」と感じられる内容です。また、退職者対応や税務上の扱いなど、実際の運用場面でも役立つ情報が詰まっており、人事・労務担当者の業務効率化にもつながります。制度の活用で、企業と従業員双方が「得する設計」がイメージできる体験を得られるでしょう。
目次
中小企業退職金共済制度(中退共)とは?
中退共(中小企業退職金共済制度)は、中小企業が従業員の退職金制度を作りやすくするために、国がサポートする制度です。この制度では、企業が毎月一定の掛金(お金)を納めるだけで、退職金を準備することができます。そのため、企業にとっては福利厚生の充実や、優秀な人材の定着にとても役立ちます。
企業が支払った掛金が「勤労者退職金共済機構」に積み立てられ、従業員が退職するときに、その積立金が退職金として支払われるという仕組みです。中小企業でも簡単に導入できるように作られており、多くの企業が利用しています。
中退共のポイントを表でわかりやすく見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営主体 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 |
| 加入対象 | 従業員のみ(パート・アルバイトも可能) |
| 掛金 | 従業員ごとに月額5,000円から設定可能 |
| 税制優遇 | 掛金は全額損金算入 |
| 国の助成 | 新規加入時や掛金増額時に一定の助成あり |
なお、経営者自身や個人事業主は中退共へ加入できません。経営者や個人事業主向けには「小規模企業共済」という別の制度が用意されています。
中退共は中小企業の企業規模に適した退職金制度として、福利厚生の充実と人材定着が期待できる制度です。
中小企業退職金共済制度(中退共)の掛金や退職金の仕組み
中退共では、企業が毎月の掛金を勤労者退職金共済機構へ納付します。勤労者退職金共済機構は退職した従業員から退職金の申請を受けると、積み立てられた掛金を退職金として支給します。ここでは掛金や退職金に関する内容について詳しく見ていきましょう。
掛金と退職金シミュレーション
中退共の掛金は、従業員ごとに月額5,000円から30,000円までの範囲で以下に記載した16種類の設定金額から選択できます。なお、パートタイマーなどの短時間労働者には2,000円と3,000円、4,000円の設定が可能です。
| 選べる掛金月額 | |
|---|---|
| 一般労働者 | 5,000円, 6,000円, 7,000円, 8,000円, 9,000円,10,000円, 12,000円, 14,000円, 16,000円, 18,000円, 20,000円 |
| 22,000円, 24,000円, 26,000円, 28,000円, 30,000円 | |
| 短時間労働者(パートタイマー等)の特例 | 2,000円, 3000円, 4000円 |
※短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員のこと
掛金は毎月積み立てられ、退職時に退職金として従業員へ支給されます。
掛金額と勤続年数に応じた退職金額の目安は、以下のとおりです。
掛金月額5,000円の場合
| 納付期間 | 掛金累計額 | 退職金額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 600,000円 | 632,800円 | 32,800円 |
| 20年 | 1,200,000円 | 1,333,300円 | 133,300円 |
| 40年 | 2,400,000円 | 2,958,950円 | 558,950円 |
掛金月額10,000円の場合
| 納付期間 | 掛金累計額 | 退職金額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 1,200,000円 | 1,265,600円 | 65,600円 |
| 20年 | 2,400,000円 | 2,666,600円 | 266,600円 |
| 40年 | 4,800,000円 | 5,917,900円 | 1,117,900円 |
掛金月額30,000円の場合
| 納付期間 | 掛金累計額 | 退職金額 | 運用益 |
|---|---|---|---|
| 10年 | 3,600,000円 | 3,796,800円 | 196,800円 |
| 20年 | 7,200,000円 | 7,999,800円 | 799,800円 |
| 40年 | 14,400,000円 | 17,753,700円 | 3,353,700円 |
掛金額が同じでも長く勤めるほど、退職金は効率よく増加します。長期勤続のインセンティブとなって、従業員の定着を促進する効果も期待できるでしょう。
退職金受取時の税制などについてはこちらの記事をご参照ください。
税制優遇により掛金が全額損金計上できる
中退共の掛金には税法上の優遇措置があり、企業は掛金全額を損金に計上できます。
中退共は退職金の原資を確保すると同時に節税効果も得られる制度設計です。掛金は企業の規模や財務状況に応じて従業員ごとに設定できるため、計画的に資金運用しましょう。
掛金を国が助成する
中退共には国からの助成金制度があり、掛金負担を軽減するサポートがあります。
助成金のタイミングと内容は以下のとおりです。
| 助成タイミング | 内容 |
|---|---|
| 新規加入 | 新規加入した事業主に対し、加入後4か月目から1年間、掛金月額の2分の1(上限5,000円)を助成 |
| 月額変更 | 掛金月額が18,000円以下の従業員について、掛金を増額した場合、増額分の3分の1を1年間助成 |
なお、地方自治体によっては中退共の加入先に対して独自の補助制度を設けている場合もあります。
該当先の一部は、中退共のホームページに掛金助成自治体等として掲載されています。自治体へ問い合わせする際の参考にしてください。掲載がない場合も、最寄りの自治体へ補助制度があるか確認することをおすすめします。
これらの助成制度が活用できると、企業は拠出する掛金負担を大幅に軽減でき、退職金制度を導入しやすくなるでしょう。
中小企業退職金共済制度(中退共)のメリット
中退共の導入には中小企業にとって多くのメリットがあります。ここでは、主な導入メリットを見ていきましょう。
小規模企業でも資金負担が少なく導入しやすい
中退共は月額5,000円から加入できるため、資金的な負担が少なく始められます。企業の財務状況に応じて掛金額を柔軟に設定できる点が大きな特徴です。
加入後4か月目から1年間、国から掛金月額の2分の1(上限5,000円)を助成金で受けられます。この助成金によって費用を抑えながら退職金制度の導入が可能です。
また、毎月定額の支払いであるため、予算管理がしやすく計画的に資金を準備できる点も小規模企業に適しているでしょう。
掛金が全額損金となる税制優遇を受けられる
中退共の掛金は全額が損金に算入できるため、企業の税負担を軽減しながら退職金を準備できます。
例えば、法人税率が23.2%の企業が10名分の掛金を月10,000円ずつ納めた場合は、以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 年間掛金総額⋯① | 120万円(=10,000円×10名×12ヶ月) |
| 節税効果⋯② | 約27.8万円(=①×23.2%) |
| 実質的な掛金負担金額(①-②) | 約92.2万円(=120万円-27.8万円) |
このように資金効率を高めながら従業員の将来に向けた準備ができます。
退職金発生時の支払い負担が軽減される
中退共の退職金は、勤労者退職金共済機構から直接支払われるため、企業が支払う必要はありません。通常の退職金と比べて、資金繰りの負担が軽減されます。
退職者が発生した場合、企業は退職金請求の手続きを補助するのみで、実際の請求は退職者本人が行います。退職者への支給も勤労者退職金共済機構から実施するため、事務手続きの負担も最小限です。
将来の退職金に備えて資金を社内に留保しておく必要がなく、計画的な資金運用が可能になります。
福利厚生制度を充実させられる
退職金制度の存在は従業員にとって将来への安心につながります。採用活動においても、「退職金制度あり」とアピールできることは強みです。
特に若手人材の採用では、福利厚生が充実している企業が選ばれる傾向があります。中退共は導入が容易なため、小規模企業でも自信をもって福利厚生をアピールできるでしょう。
また、退職金という将来の保障があることで従業員の定着率向上も期待できます。長期的な人材確保と人材育成につながる重要な制度です。
確定給付企業年金(DB)より導入しやすい理由
中退共はDBと比較して、中小企業が導入しやすい退職金制度です。両者の違いを理解し、自社に適した退職金制度を選択しましょう。
導入コストが低く手間が省ける
DBは企業が自ら資産運用を行い、約束した退職金額を支払う責任があるため、年金数理人や運用コンサルタントの運用コストが必要です。
一方で、中退共は国の機関が運営するため、企業側での資産運用業務がなく運用コストがかかりません。
中退共とDBの運用コストにかかる主な違いを見ていきましょう。
| 中退共 | DB | |
|---|---|---|
| 導入コスト | 掛金のみ | 掛金+専門家報酬+運用管理費 |
| 事務手続き | 加入申込と掛金納付のみ | 年金規約作成、認可申請 |
| 運用管理 | 国が一括管理 | 企業または企業年金基金が管理 |
| 国からの助成金 | 新規加入時・掛金増額時に有り | 無し |
中退共では複雑な手続きが省略できるため、管理する担当者の負担を大幅に軽減できます。
また、運用管理を企業が負わなくてよいという安心感もあります。一方、DBでは運用が悪化した場合、企業が追加資金を拠出して補填する必要が生じかねません。
企業規模によって導入のしやすさが異なる
企業規模が小さいほど、退職金制度の導入や維持にかかる負担が変わります。
DBは小規模企業にとって、導入して維持することは大きな負担です。一方で、中退共は小規模企業でも導入しやすく続けやすい制度設計です。
運用や管理の専門知識が不要で、手続きも簡単なため、労務担当者を置けない小規模企業にとって大きなメリットがあります。
また業種による制限も少なく、製造業からサービス業まで幅広い業態で活用できます。従業員の退職金を準備しつつ、管理負担を軽減したい小規模企業の経営者が考えるニーズにあう退職金制度です。
なお、将来的に企業規模が拡大した場合、DBへの移行は可能なため、成長段階に応じた柔軟な対応ができるでしょう。
中小企業退職金共済制度(中退共)のデメリット
中退共は、いくつかの制約やデメリットも存在します。導入を検討する際には、これらの点も考慮して判断することが大切です。
掛金を全額負担する
中退共の掛金は、企業が全額負担する必要があります。従業員の給与から天引きして一部を負担してもらえません。
経営が厳しい企業では、全従業員分の掛金を拠出することが資金繰りを逼迫させる原因となりえます。掛金の支払いは常に継続するため、掛金の金額は無理のない範囲で設定しましょう。
税制優遇のメリットは魅力的ですが、毎月の掛金総額が企業の資金繰り負担になることを考慮しておく必要があります。
従業員ごとに個別対応が必要
中退共は従業員単位で加入手続きや脱退手続きなどが必要です。従業員数の増減に合わせて、その都度手続きしなければなりません。
主な手続きは、以下のとおりです。
| 手続き | 必要な時期 | 主な書類 |
|---|---|---|
| 新規加入 | 従業員雇用時 | 退職金共済契約申込書 |
| 脱退手続き | 従業員退職時 | 退職金共済契約解除申出書 |
| 従業員情報変更 | 氏名・住所変更時 | 被共済者氏名等変更届 |
従業員が多い企業では、従業員ごとに必要となる手続きの煩雑さが、担当者の業務負担につながります。まとめて申請するなど社内ルールで仕組みを設定すると効率化により業務負担を軽減できるでしょう。
掛金の増減に申請が必要
毎月の掛金を変更する場合は、変更月の前月15日までに書類提出が必要です。月ごとの申請であるため、柔軟に掛金を変更できません。
例えば、4月に急な経営悪化で資金繰りが逼迫して15日以降に掛金を減額しようとした際、掛金の変更は6月以降となります。また、掛金を増額または減額のどちらも手続きが必要ですが、減額の場合は、一定の条件を満たさないと認められないケースがあります。
変更のたびに書類作成や申請の手間がかかるため、頻繁な変更は避けるようにしましょう。
退職金額は一定のルールに基づく
中退共の退職金額は法令で定められた計算式に基づいて算出されます。企業独自の退職金制度のような柔軟な設計はできません。
退職金は「基本退職金」と「付加退職金」の合計で構成されます。基本退職金は掛金と勤続年数から算出され、付加退職金は運用益から支給される仕組みです。
長期勤続者に有利な設計となっているため、短期間で退職する従業員にとっては魅力が薄く感じる制度です。また、企業の功労者に特別な退職金を用意するといった対応も制度へ含められないため注意しましょう。
中小企業退職金共済制度(中退共)の導入方法
中退共の導入ステップは以下のとおりです。
- 申込書の入手
- 掛金設定
- 申込書類一式を提出
- 掛金納付開始
それぞれのステップについて解説します。
Step1:申込書の入手
中退共の申込書は複数の方法で入手できます。
| 入手方法 | 入手先 |
|---|---|
| 窓口 | 最寄りの金融機関または商工会議所や商工会などの委託団体窓口 |
| 郵送 | 中小企業退職金共済制度(中退共)公式サイトの資料請求から必要情報を入力して資料請求 |
| インターネット | 中小企業退職金共済制度(中退共)公式サイトからPDF書式をダウンロード |
金融機関のうち、ゆうちょ銀行や農協、漁協、ネット銀行、外資系銀行は含まれません。インターネットでのダウンロードが、必要な書類一式をまとめて入手できる最も手軽な方法でしょう。
Step2:掛金設定
従業員ごとに月額掛金を決定し、掛金月額は5,000円から30,000円までの範囲で16種類ある金額から設定できます。なお、パートタイマーなどの短時間労働者には2,000円と3,000円、4,000円の設定が可能です。
| 選べる掛金月額 | |
|---|---|
| 一般労働者 | 5,000円, 6,000円, 7,000円, 8,000円, 9,000円,10,000円, 12,000円, 14,000円, 16,000円, 18,000円, 20,000円, 22,000円, 24,000円, 26,000円, 28,000円, 30,000円 |
| 短時間労働者(パートタイマー等)の特例 | 2,000円, 3000円, 4000円 |
※短時間労働者とは、いわゆるパートタイマー等1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の従業員より短く、かつ30時間未満である従業員のこと
掛金設定のポイントは以下のとおりです。
- 全員同額の必要はなく、役職や勤続年数に応じて設定できる
- 会社の財務状況に合わせて無理のない金額に設定する
- 将来の昇給に備えて余裕をもった設定を検討する
退職金制度があることは企業と従業員それぞれに魅力的ですが、経営状況に合わせた掛金設定が継続のために重要になります。
Step3:申込書類一式を提出
必要書類をすべて揃えて最寄りの金融機関または委託団体へ提出します。主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 退職金共済契約申込書(新規用) | 会社情報と従業員情報を記入 | 従業員の生年月日を正確に記入 |
| 預金口座振替依頼書 | 掛金引落口座の情報 | 金融機関の届出印が必要 |
| 中小企業者であることの証明書 | 中小企業の要件を満たす証明 | 税務署の証明など |
書類に不備があると、照会や返送後の再送手続きなどによって加入手続きが遅れるため、記入漏れがないよう提出前に確認しましょう。
Step4:掛金納付開始
申込書類の処理が完了すると、指定した銀行口座から毎月18日に掛金が自動で引き落とされます。納付方法は、掛金の振り替えタイミングが当月または翌月かを選択可能です。
振替日には十分な資金を確保しておく必要があります。預金残高が不足すると、自動引き落としされずに翌月以降の掛金へ加算して振り替えられます。
なお、初めての申し込みをして最初の掛金納付開始は、申し込み付きの翌月または翌々月を目安にしておきましょう。最初の振り替えでは申込月分から初回振替月分まで一括振替となるため注意が必要です。
中小企業退職金共済制度(中退共)による退職金手続きの注意点
中退共の退職金は退職した従業員から請求手続きしますが、企業側は補助的な役割があります。ここでは、中退共へ退職金を請求する際の注意点を見ていきましょう。
退職者の受給資格を確認する
退職金を受け取るには、中退共への加入期間が1年以上である条件を満たす必要があります。従業員が退職金の請求手続きできるよう、受給資格の確認が欠かせません。
受給資格が有る場合には、退職した従業員へ退職後1年以内に請求手続きするように伝えましょう。退職後1年以上経過すると時効により請求権が消滅するリスクがあるため早めの手続きが大切です。
退職者へ必要書類を渡す
退職金の受け取りに必要な書類は、以下のとおりです。
| 書類名 | 対応内容 |
|---|---|
| 被共済者退職届 | ・企業から勤労者退職金共済機構へ提出 ・退職金共済手帳の2枚目を使用 ・書留郵便又は特定記録郵便で郵送 |
| 退職金共済手帳 | 企業から従業員へ退職時に交付 |
| 退職金請求書 | ・従業員から勤労者退職金共済機構へ提出 ・退職金共済手帳の3枚目を使用 ・書留郵便又は特定記録郵便で郵送 |
企業は被共済者退職届を従業員の退職が決まると忘れずに提出する必要があります。また、退職金請求書の右上にある事業主欄も漏れずに記入して証明します。
従業員はマイナンバー入り住民票と本人確認書類(運転免許証のコピーなど)の添付も必要です。
退職者へ退職金にかかる税金について伝える
中退共の退職金は退職所得として扱われ退職所得控除があるため、税負担が軽くなります。
退職所得控除額は以下のとおりです。
- 勤続20年以下は勤続年数×40万円
- 勤続年数20年超は800万円+(20年超の年数×70万円)
なお、勤続年数は掛金を納付した期間で判断されます。
退職金を受け取る際には「退職所得の受給に関する申告書」を提出しますが、中退共制度では「退職金(解約手当金)請求書」に含まれているため、改めての対応は必要ありません。
退職者には、退職金受取前に税金や手続きについての説明が重要です。
この記事のまとめ
中退共は中小企業にとって心強い制度ですが、「いざ導入」となると、掛金の最適設定や他の節税制度とのバランスなど、個別判断が必要な場面も多くあります。例えば、法人保険や小規模企業共済との組み合わせ、退職金制度を軸にした長期的な福利厚生戦略、さらに事業承継に向けた資金計画への応用も視野に入るでしょう。制度を“ただ導入する”だけでなく、“最大限活かす”ためには、経営全体を見渡した専門的なアドバイスが不可欠です。信頼できる資産運用や企業制度に詳しい専門家に相談することで、自社に合った設計が見えてきます。まずは一度、貴社の将来と従業員の安心を支えるための第一歩として、専門家との対話を始めてみませんか?

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
中退共(中小企業退職金共済制度)
中退共とは、中小企業の従業員に退職金を支給するための共済制度です。企業が毎月掛金を支払い、従業員が退職する際に積み立てられた退職金が支給されます。国の助成金もあり、企業負担を軽減しながら従業員の退職後の生活を支えます。
独立行政法人勤労者退職金共済機構
独立行政法人勤労者退職金共済機構(略称:勤退共機構)は、中小企業の退職金制度を支援する公的機関です。中小企業が加入する中小企業退職金共済制度(中退共)の運営や、建設業・清掃業向けの退職金共済制度の管理を担っています。
掛金
掛金とは、保険や年金、共済制度などにおいて、契約者が定期的に支払う金額のことを指します。例えば、国民年金や厚生年金の掛金(保険料)は、将来の年金給付のために積み立てられます。また、企業型確定拠出年金(DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)では、加入者が掛金を拠出し、その運用結果に応じた給付を受け取ります。掛金の金額や支払方法は制度ごとに異なり、法律や契約内容によって定められています。
損金
損金とは、法人税の計算上、企業の所得から控除できる費用のことを指す。具体的には、給与、仕入原価、広告宣伝費、減価償却費などの事業に直接関連する支出が該当する。損金に計上できるかどうかは税法により定められており、計上可能な費用を適切に処理することで課税所得を抑えることができる。一方で、税務上の損金と会計上の費用が一致しない場合もあり、適切な管理が求められる。
給付金
給付金とは、特定の条件を満たした場合に支給される金銭のことを指します。主に公的機関や保険会社が支払うもので、社会保障制度に基づくものや、保険契約に基づくものがあります。例えば、医療保険では入院や手術時に給付金が支払われ、失業保険では失業中の生活支援として給付金が提供されます。支給条件や金額は制度や契約内容によって異なり、受け取るためには申請が必要な場合が多いです。
福利厚生
福利厚生とは、企業が従業員に対して給与以外に提供する各種サービスや支援制度です。健康保険、退職金制度、住宅手当、育児支援などが含まれます。福利厚生は、従業員の生活を支え、働きやすい環境を提供することで、企業への定着率向上にもつながります。
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。
年金数理人(アクチュアリー)
年金数理人(アクチュアリー)とは、年金制度の設計や運営において、将来の年金給付額や保険料の適正性を計算・分析する専門家です。確率や統計の手法を使って、年金制度が持続可能であるかを評価し、必要な調整を提案します。年金数理人(アクチュアリー)の分析は、年金制度の安定運営に欠かせません。
退職所得控除
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に税金を軽くしてくれる制度です。長く働いた人ほど、退職金のうち税金がかからない金額が大きくなり、結果として納める税金が少なくなります。この制度は、長年の勤続に対する国からの優遇措置として設けられています。 控除額は勤続年数によって決まり、たとえば勤続年数が20年以下の場合は1年あたり40万円、20年を超える部分については1年あたり70万円が控除されます。最低でも80万円は控除される仕組みです。たとえば、30年間勤めた場合、最初の20年で800万円(20年×40万円)、残りの10年で700万円(10年×70万円)、合計で1,500万円が控除されます。この金額以下の退職金であれば、原則として税金がかかりません。 さらに、退職所得控除を差し引いた後の金額についても、全額が課税対象になるわけではありません。実際には、その半分の金額が所得とみなされて、そこに所得税や住民税がかかるため、税負担がさらに抑えられる仕組みになっています。 ただし、この退職所得控除の制度は、将来的に変更される可能性もあります。税制は社会情勢や政策の方向性に応じて見直されることがあるため、現在の内容が今後も続くとは限りません。退職金の受け取り方や老後の資産設計を考える際には、最新の制度を確認することが大切です。
損金算入
損金算入とは、企業が支払った経費のうち、税務上の所得計算において課税対象から控除できる金額のことです。例えば、事業活動に必要な経費や接待交際費の一部は損金算入の対象となります。損金算入により、企業の課税所得が減少し、納める法人税が軽減されます。
掛け捨て保険
掛け捨て保険とは、一定期間の保障を得ることに特化した保険で、保険期間が終わった後に保険料が戻ってこないタイプの保険です。代表的なものに、定期型の生命保険や医療保険があります。保障が必要な期間に絞って加入できるため、毎月の保険料を安く抑えられるのが大きな特徴です。貯蓄機能はないものの、万一に備えるコストパフォーマンスが高く、特に子育て世代や住宅ローン返済中など、一時的に大きな保障を必要とする方に適しています。「お金が戻らないから損」と感じる方もいますが、必要な時期に必要な保障を効率よく確保する手段として、多くの方に利用されています。
法人保険
法人保険とは、会社が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする保険のことです。会社が支払う保険料は、保障を通じて従業員の万一に備えるだけでなく、福利厚生としての活用や、役員退職金の準備、さらには事業承継対策にもつながります。 また、保険の種類や契約内容によっては、支払った保険料の一部または全部が経費(損金)として処理できる場合もあります。ただし、税制やルールは変更されることもあるため、導入にあたっては専門家のアドバイスを受けることが大切です。企業の財務戦略の一環として、保障と資産管理をバランスよく行いたい企業に活用されています。