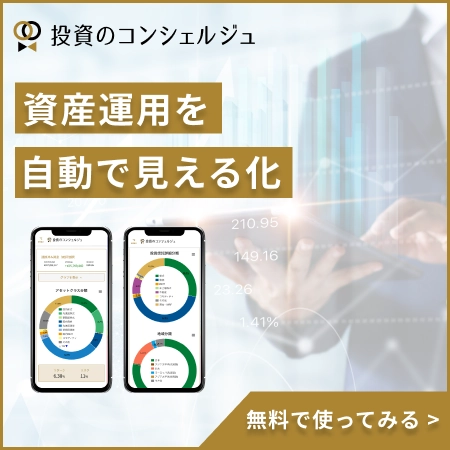経済指標の基礎知識|投資初心者が見るべ重要指標を徹底解析
難易度:
執筆者:
公開:
2025.03.31
更新:
2025.04.03
株や債券に投資するうえで、「なぜ今この銘柄が上がるのか」「金利が動く背景は?」と疑問に思ったことはありませんか?その答えを解く鍵が“経済指標”です。CPIやGDP、失業率などの経済データは、マーケットの動きに直結する「投資の羅針盤」。この記事では、投資初心者でも押さえておきたい主要経済指標を丁寧に解説し、日々の相場を読み解く力が身につく内容をお届けします。
サクッとわかる!簡単要約
本記事を読むことで、ただの数字の羅列だった経済指標が、投資判断に直結する「意味ある情報」に変わります。例えばGDPの伸びが示す景気の波や、CPIの数値から見える金利の動き、失業率やPMIの変化が企業業績や相場にどのように影響するのかが腑に落ちるようになるでしょう。さらに、指標の発表タイミングや市場への反応、どの指標が株に強く影響し、どれが債券に効くのかまで理解できるようになります。初心者でも「ニュースが読める」「相場の先を考えられる」ようになリマス。まさに「投資家としての視点」が得られる実践的な内容です。
主要経済指標とその解説
投資をするうえで、経済指標の理解は欠かせません。GDPやCPI、失業率、政策金利などの指標は、市場の動きを予測し、適切な投資判断を行うための重要な手がかりとなります。それぞれの指標が示す意味や市場への影響を知ることで、投資のリスクを抑え、より戦略的な資産運用が可能になります。ここでは、主要な経済指標の特徴や公表タイミング、投資判断への活用方法について詳しく解説します。
タイトル:投資判断に必要な主要経済指標の概要
| 指標 | 公表主体 | 公表頻度 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| GDP(国内総生産) | 内閣府(日本)・BEA(米国) | 四半期 | 景気拡大なら株価上昇、景気後退なら株価下落 |
| CPI(消費者物価指数) | 総務省統計局(日本)・BLS(米国) | 毎月 | インフレ率が高ければ利上げ圧力で株・債券に影響 |
| 失業率 | 総務省統計局(日本)・BLS(米国) | 毎月 | 低下は景気拡大を示し株価上昇、上昇は景気減速の兆候 |
| 政策金利 | 日本銀行・FRB(米国) | 年8回程度 | 利上げで株価下落・債券価格下落、利下げで逆の動き |
| PMI(購買担当者景気指数) | Jibun銀行(日本)・ISM(米国) | 毎月 | 50以上で景気拡大期待、50以下で景気減速懸念 |
| 小売売上高 | 経済産業省(日本)・商務省(米国) | 毎月 | 消費拡大で株価上昇、消費減速で株価下落 |
GDP(国内総生産)
特徴
GDP(Gross Domestic Product:国内総生産)は、一定期間に国内で新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の合計を示す指標です。簡単に言えば、国の経済規模を表す基本的なデータです。
GDP成長率(前期比・前年比)がプラスであれば景気が拡大していることを意味し、マイナスであれば景気が後退していることを示します。
公表タイミング
一般的に四半期ごと(3カ月ごと)に公表されます。例えば日本では内閣府が四半期ごとのGDP統計を発表し、米国では商務省経済分析局(BEA)が四半期ごとに速報値・改定値・確報値の3段階で公表します。速報値は特に注目され、発表時には市場が大きく動くこともあります。
公表主体
国ごとに政府の統計機関が担当します。日本では内閣府経済社会総合研究所がGDPを算出・公表し、米国では商務省経済分析局(BEA)が発表しています。
投資判断への活用方法
GDPは経済全体の健康状態を示すため、株式市場・債券市場ともに強い関心を寄せています。GDP成長率が高い(景気拡大局面)場合、企業業績の向上が期待され株価上昇につながりやすいでしょう。
一方で経済が加熱しすぎると中央銀行が利上げを検討するため、将来の金利上昇観測から長期債券の価格下落(利回り上昇)を招く場合もあります。
逆にGDP成長率がマイナスとなり景気後退が懸念される場合、株式市場では企業業績悪化への懸念から株価が下落しやすくなります。その反面、中央銀行の景気刺激策(利下げなど)への期待から債券には買いが入る(利回り低下=価格上昇)傾向があります。
つまりGDPが好調か低迷かで株式と債券の資産配分を考えるヒントになります。
CPI(消費者物価指数)
特徴
CPIはConsumer Price Indexの略で、消費者が購入する商品の価格水準の変動を示す物価指数です。景気が良くなれば物価が上昇し、景気が悪くなれば物価が下落する傾向があるため、CPIは「経済の体温計」とも呼ばれます。インフレ率(物価上昇率)を把握する代表的な指標であり、中央銀行が金融政策を決める際にも重視されます。
公表タイミング
毎月公表されます。例えば日本では総務省統計局が毎月下旬に消費者物価指数を発表し、米国では労働統計局(BLS)が月次のCPIを発表します。通常、前月分のデータが翌月に公開される形です。
公表主体
日本では総務省統計局、米国では労働省労働統計局(BLS)など、公的統計機関が算出しています。地域によっては都市部と全国のCPIが別々に公表されることもあります(例えば日本の「全国CPI」と「東京CPI」など)。
投資判断への活用方法
CPIはインフレ動向を示すため、債券投資との関係が特に深い指標です。インフレ率が中央銀行の目標(例えば日本 Bank of Japan の物価目標2%)を上回るような高インフレ局面では、利上げによる抑制策が取られる可能性が高まります。
利上げは既存債券の価格を下げ(新発債の利回りが相対的に高くなるため)、債券にはマイナス材料となります。また金利上昇局面では企業の借入コスト増加や個人消費の減速を通じて株式市場にも下押し圧力がかかりやすくなります。
一方、インフレ率が低迷しデフレ懸念が強まる場合、中央銀行は利下げや量的緩和など景気刺激策を検討するため、債券価格には追い風となりがちです。ただしデフレは企業の売上減少にもつながるため、極端な物価下落は株価にとっても望ましくありません。
一般に適度なインフレ(緩やかな物価上昇)は企業収益拡大と金利安定のバランスが取れた状態であり、株式・債券双方にとって受け入れやすい環境と言えるでしょう。
失業率
特徴
失業率は労働力人口(働く意思と能力のある人)のうち仕事に就いていない人の割合を示す指標です。景気の良し悪しが直ちに反映されやすい雇用情勢の代表的な統計で、景気拡大期には失業率が低下し、景気後退期には上昇する傾向があります。失業率は「完全失業率」とも呼ばれ、労働市場の健全性を測るバロメーターです。
公表タイミング
多くの国で毎月公表されます。日本では総務省が労働力調査として毎月末に前月の失業率を発表します。米国では月初(通常毎月第1金曜日)に米国労働省が前月の失業率を発表します。
公表主体
各国の労働統計機関が担当しています。日本では総務省統計局、米国では労働省労働統計局(BLS)が該当します。欧州でも各国の統計局やEU統計局(ユーロスタット)が失業率を公表しています。
投資判断への活用方法
失業率は景気の遅行指標とも言われ、景気変動にやや遅れて動く傾向がありますが、その水準や動きは金融政策や市場心理に大きな影響を及ぼします。
例えば失業率が低下して歴史的低水準になると、労働需給の逼迫から賃金上昇・個人消費拡大が期待でき、企業収益にもプラスとなるため株価に好材料です。同時に賃金上昇によるインフレ圧力が高まるため、中央銀行が利上げを検討する可能性もあり、将来の金利上昇観測から債券市場では利回りが上昇しやすくなります。
逆に失業率が上昇している局面では、景気減速や企業業績悪化のシグナルと受け止められ株式市場にはマイナス材料となりますが、その分金融緩和策への期待が高まり債券は買われやすくなるという関係があります。また米国の場合、FRB(米連邦準備制度理事会)は「物価の安定」と並んで「雇用の最大化」を政策目標に掲げており、失業率など雇用指標の結果は金融政策の決定に大きく影響します。したがって投資家も失業率の変化には注意を払い、将来の金利動向や景気動向を読み解く材料にします。
中央銀行の政策金利
特徴
政策金利とは中央銀行が市中金利に影響を与えるために操作する基準金利のことです。ここでは特に米国のFOMC(連邦公開市場委員会)による政策金利発表を指します。FOMCはFRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策決定会合であり、ここでフェデラルファンド金利(FF金利)の誘導目標、すなわち米国の政策金利水準が決定されます。政策金利の変更(利上げ・利下げ)は金融市場に極めて大きな影響を持つため、その発表は最重要イベントの一つです。
公表タイミング
年8回程度開催される定例の中央銀行会合に合わせて発表されます。米国のFOMCは通常6週間おき(年8回)に開催され、会合最終日に政策金利変更の有無を含む声明が公表されます(声明公表後、FRB議長による記者会見も行われます)。日本銀行も「金融政策決定会合」を年8回開いており、同様に政策金利や金融緩和策の方針を発表しています。主要な中央銀行(欧州中央銀行やイングランド銀行など)も定期的に政策金利を審議・発表しています。
公表主体
各国の中央銀行です。米国の場合はFRBがFOMC声明という形で発表し、日本では日本銀行が金融政策決定会合の結果として発表します。欧州中央銀行(ECB)など他国・地域でも中央銀行が担います。
投資判断への活用方法
政策金利の動向は株式・債券の双方に直結します。例えば中央銀行が利上げを決定した場合、短期金利の上昇によって銀行の貸出金利や企業の調達コストが上がり将来的な経済活動の減速要因となるため、株式市場ではネガティブに捉えられやすいです。また利上げは既存債券の利回りを相対的に低くしてしまうため債券価格の下落要因でもあります。一方で利下げが発表された場合、資金調達コストの低下による景気刺激が期待され株価には追い風となりやすく、債券も利回り低下(価格上昇)という形で好影響を受けます。特に債券は金利と逆相関の関係にあるため、金融引き締め局面では売り、金融緩和局面では買いという動きが顕著です。また、市場は将来の政策金利動向を予想して織り込むため、投資家は中央銀行トップの発言や声明文の文言変化にも敏感になります。初心者の方は、まず政策金利の引き上げ・引き下げが与える一般的な影響を押さえつつ、発表前に市場コンセンサス(予想)を確認し、実際の発表結果との差異にも注目するとよいでしょう。
PMI(購買担当者景気指数)
特徴
PMI(Purchasing Managers’ Index、購買担当者景気指数)は、企業の購買担当者に対して行うアンケート調査結果から算出される景気指標です。新規受注、生産、雇用の状況などについて企業の購買担当者に聞き取りを行い、その結果を指数化しています。景況感を敏感に映し出す先行指標の一つで、50を境目として50を上回れば景気拡大、50を下回れば景気減速を示すとされます。製造業PMIと非製造業(サービス業)PMIに分かれて公表されますが、特に製造業の動向が注目される傾向があります。
公表タイミング
毎月発表されます。調査主体によって発表タイミングは若干異なりますが、多くの場合月初(当月または翌月初)に前月の調査結果が公表されます。例えばアメリカでは民間の供給管理協会(ISM)やS&Pグローバル(旧IHSマークイット)が月初に製造業PMI・非製造業PMIを発表し、中国でも毎月末~月初に国家統計局などが製造業PMIを公表します。日本では日銀短観とは別に、Jibun銀行とS&Pグローバルが共同で月次PMIを発表しています。
公表主体
国や地域ごとに民間団体や業界団体が調査・公表します。代表的なものとして、米国のISM(全米供給管理協会)やイギリスのS&Pグローバル(旧IHS Markit)が各国・地域のPMIを集計しています。中国では国家統計局など公的機関が関与するPMIも存在します。公的統計ではありませんが、市場への影響力が大きいため広く注目されています。
投資判断への活用方法
PMIは景気の先行きをいち早く把握できる指標として株式投資で活用されます。例えば製造業PMIが50以上で上昇基調にあれば製造業を中心に景気拡大が示唆され、関連企業の株価上昇が期待できます。PMIが市場予想を上回ると景気に明るい見通しを与えるため株式市場には好材料となることが多いです。逆にPMIが50を割り込んで低下傾向に入ったり、市場予想を下回るような場合は景気減速懸念から株価の下押し要因となりえます。債券投資の観点では、PMI低迷により景気後退が意識されれば将来的な利下げ観測から債券利回りが低下(価格は上昇)しやすくなります。またPMIは高頻度(月次)のため、四半期ごとのGDPを待たずに機動的に投資判断を調整する材料としても使われます。先行指標とはいえ単月のブレもあるため、数カ月間のトレンドとして上向きか下向きかを見極めることが重要です。
ISM製造業景況指数(米国ISM PMI)
特徴: ISM製造業景況指数は、上述したPMIの一種で米国の製造業PMIにあたります。全米供給管理協会(ISM)が製造業の購買担当者に対するアンケート調査結果をまとめて指数化したもので、米国製造業の景況感を示す代表的な指標です。項目は新規受注、生産、高度な雇用、入荷遅延、在庫など多岐にわたり、50を基準に景気拡張か縮小かを判断します。特にISM指数は景気の先行きを示す重要な手掛かりとして、米国のみならず世界の市場参加者が注目します。
公表タイミング
毎月第1営業日に前月の指数が発表されます。例えば1月分のISM製造業指数は2月初旬(通常1日か最初の営業日)に公表されます。これは主要経済指標の中でも比較的早いタイミングで発表されるため、マーケットに与える初動インパクトが大きいです。非製造業(サービス業)のISM指数は製造業の数日後に発表されます。
公表主体
米国の非営利団体である全米供給管理協会(Institute for Supply Management, ISM)が調査・公表しています。民間統計ではありますが、歴史が長く信頼性が高いため公的統計と同等に扱われます。
投資判断への活用方法
ISM製造業指数は米国経済の動向を占う上で欠かせない指標であり、その結果は株式市場に即座に反映されることがあります。例えばISM指数が市場予想を上回り製造業の拡大基調が確認されれば、景気敏感株を中心に株価が上昇しやすくなります。逆に予想を下回る弱い数字であれば、景気減速懸念から株式全般が売られることもあります。債券市場にとっても、強いISM指数は将来的な金利上昇余地を意識させ債券利回りの上昇(価格下落)要因となり得ます。一方、ISM指数の大幅悪化は景気後退→利下げ期待につながり債券利回り低下(価格上昇)要因となる場合があります。ISM指数は月次変動が大きいこともあるため、単月の結果に一喜一憂しすぎず、3ヶ月程度の移動平均や他の指標と併せて総合的に判断することが肝要です。
小売売上高
特徴
小売売上高は、百貨店やスーパー、飲食店など小売業とサービス業の売上高合計を示す指標で、個人消費の動向を測る代表的な経済指標です。消費者がどれだけお金を使ったかが分かるため、景気の即時的な強さを知ることができます。特に米国では個人消費がGDPの約7割を占めるため、小売売上高のデータから米国景気を占うことが可能です。
公表タイミング
毎月発表されます。米国の小売売上高(Retail Sales)は商務省のセンサス局が毎月中旬頃に前月分を公表します。日本では経済産業省が「商業動態統計(小売業販売額)」として毎月下旬~翌月初めに公表しています。いずれも前月の個人消費の状況をタイムリーに把握できる指標です。
公表主体
米国では商務省・センサス局、日本では経済産業省といった政府機関が担当します。欧州でもEU統計局や各国統計局が小売売上高を発表しています。民間調査ではないため、統計手法や対象範囲が国によって若干異なる点には注意が必要です。
投資判断への活用方法
小売売上高は企業の売上に直結する消費動向を示すため、株式市場への影響が大きい指標です。売上高が堅調に伸びている場合、消費関連企業(小売業、サービス業など)の業績拡大が期待され株価上昇につながりやすくなります。
また、消費の旺盛さは景気全体の好循環を意味するため、幅広い業種にとってプラス材料です。逆に小売売上高が落ち込んでいるときは、個人消費の減速→企業業績悪化懸念から株価の下押し要因となります。特にクリスマス商戦や年末年始など重要な時期の売上データはマーケットの注目度が高く、結果次第で大きく相場が動くこともあります。
債券投資の観点では、消費低迷が明らかになれば景気減速→金融緩和期待から債券が買われる可能性がありますし、消費が好調すぎればインフレ加速→利上げ警戒から債券が売られるという間接的な影響が考えられます。小売売上高は変動が激しい月もあるため、前年同月比や移動平均で基調を判断することも有効です。
ISM非製造業景況指数(サービス業指数)
特徴
ISM非製造業景況指数は米国サービス業の景況感を示す指数で、サービス業版のPMIです。小売や金融、医療など製造業以外の幅広い業種を対象にしており、米国経済全体の約7割を占めるサービス部門の動向を把握できます。50が景気拡縮の分岐点で、製造業指数と同様に景気の先行指標とされています。
公表タイミング
毎月第3営業日頃に前月分が公表されます。製造業指数の2営業日後程度に発表されることが多いです。
公表主体
ISM(全米供給管理協会)が製造業指数と同じ調査フレームで非製造業版として公表しています。
投資判断への活用方法
サービス業指数は内需型企業(流通、小売、ITサービスなど)の業績見通しと関連が深いため、株式投資ではこちらも重要です。例えばサービス業指数が好調であれば内需株に買いが入りやすく、逆に低迷するとそれらの株価にマイナス材料となります。債券市場への影響は製造業指数と概ね同様で、強い結果は利上げ思惑、弱い結果は利下げ思惑につながります。製造業と非製造業の両方を見ることで、経済全体のバランスを把握することができるでしょう。
その他初心者が注目すべき指標
上記以外にも、投資初心者が押さえておくと良い経済指標はいくつかあります。代表的なものを追加でご紹介します。
日銀短観(企業短期経済観測調査)
日本銀行が年4回(3月・6月・9月・12月)に公表する国内企業の景況感調査です。資本金2,000万円以上の企業約1万社を対象に「現在の景気判断」「先行き予想」「設備投資計画」などをアンケート集計します。
特に注目される指標は業況判断DI(景気が「良い」と答えた企業割合から「悪い」と答えた割合を引いた指数)で、景気の風向きを敏感に示します。短観は調査期間から公表まで1ヶ月程度と速報性が高く、結果は株式市場にも強い影響を与えます。
DIがプラス圏で上昇傾向なら景気拡大期待から株価にプラス、マイナス幅拡大なら景気悪化懸念で株価にマイナスとなる傾向があります。債券市場でも景気指標として受け止められ、強い結果は利回り上昇(価格下落)、弱い結果は利回り低下(価格上昇)の材料となり得ます。
消費者信頼感指数(消費者マインド)
消費者の景気に対する信頼感や将来の収入見通しに関するアンケート調査から算出される指数です。例えば米国では民間調査機関(コンファレンス・ボード社など)が毎月消費者信頼感指数を発表し、個人消費の先行きを示す指標として注目されています。
日本でも内閣府が「消費者態度指数」を毎月公表しています。消費者マインドが改善すると耐久財購入などにつながりやすく、株式市場ではプラス材料です。悪化すれば消費手控えが予想され、小売・サービス関連株にマイナス影響が懸念されます。債券投資ではあまり直接取り上げられませんが、消費マインド低下→景気減速→金融緩和期待という連想で債券にプラスとなる可能性があります。
この他にも鉱工業生産指数(生産活動の動向を見る指標)や景気動向指数(複数指標の総合的な景気判断指数)、貿易収支(輸出入の差額から外需動向を把握)など、多くの経済指標があります。それぞれ特徴がありますが、初心者の方はまず景気・雇用・物価・金融政策に関する主要指標から優先的にチェックすると良いでしょう。
投資における経済指標の活用方法
経済指標を投資判断に活かす際には、以下のポイントに注意すると良いでしょう。
経済カレンダーを活用
各経済指標の発表日時はあらかじめ決まっているため、経済カレンダーをチェックして重要指標の発表日を把握しましょう。特にマーケットに与える影響が大きい指標(雇用統計やFOMCなど)は発表前後で株価や金利が変動しやすいので、ポジション管理に気を配ります。
市場予想との比較
指標そのものの数値以上に市場予想との差が価格変動をもたらすことが多々あります。たとえば事前予想より良い結果が出ればポジティブサプライズ、悪い結果ならネガティブサプライズとして市場が反応します。実際に公表された数値が事前予想から大きく外れると株価に影響を及ぼすことがあります。したがって指標発表の際には、単に「良い・悪い」だけでなく予想比でどうだったかを確認する習慣をつけましょう。
単月の数字よりトレンドを重視
経済指標は一回分の数値だけでは判断せず、直近数ヶ月~数四半期の推移を見ることが重要です。単月の特殊要因(例:天候不順で消費低迷、一時的な統計方法変更など)でブレる場合があるためです。トレンドとして改善傾向にあるのか、悪化傾向にあるのかを掴むことで、より精度の高い景気判断と投資判断が可能になります。
指標間の関連性を理解
複数の経済指標を組み合わせて総合的に景気判断を行う視点も大切です。たとえば「雇用は好調だがインフレが高進している」という場合、株式にはプラスとマイナスの要因が混在します。このように指標ごとの影響が一致しないケースもあるため、経済全体のバランスを見ることが肝要です。
マーケットの織り込みと過剰反応に注意
指標の数値どおりに株価や金利が動くとは限りません。市場は常に将来を織り込んで動いており、指標結果はすでに株価に反映済み(織り込み済み)の場合や、他の要因(地政学リスクや企業業績など)が優先されて指標通りに動かない場合もあります。また、指標発表直後は短期筋の売買で過剰反応し、その後冷静に戻るようなケースもあります。したがって指標発表の瞬間的な値動きに振り回されず、落ち着いて本質を見極める姿勢が求められます。
長期視点を忘れない
経済指標は短期的な売買戦略にも役立ちますが、中長期の資産運用では「景気サイクルを読む」材料として活用するのがおすすめです。株式や債券の比率調整、業種配分の見直しなどに経済指標の示すトレンドを反映させることで、大きな景気の波に乗る投資ができるでしょう。
この記事のまとめ
経済指標を理解することは、相場に振り回されないための「土台」です。ただし、それぞれの指標が意味することや相場への影響を具体的なポートフォリオに反映させるには、一定の知識と戦略が求められます。とくに住宅ローンを抱えながら、子どもの進学費や老後資金を考える世代にとって、金利や景気動向の変化は無視できないリスク要因です。今回の記事で得た知識を「自分の資産運用」に活かすには、専門家の視点を借りるのが効果的です。あなたの家計状況や将来の目標に合わせて、経済環境を味方につける資産設計を始めてみませんか?

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連質問
関連する専門用語
経済指標
経済指標は、国や地域の経済の状態を評価するために使用されるデータや数値です。これには国内総生産(GDP)が含まれ、これは一定期間内に国内で生産された財とサービスの総価値を示し、経済の全体的な規模と成長を測ります。失業率も重要な指標で、労働力人口の中で仕事を求めているが就職できていない人々の割合を示し、経済の健康状態を反映します。また、インフレ率は物価の変動を示し、消費者物価指数(CPI)に基づいて算出され、物価の安定性や通貨の価値を評価するのに役立ちます。 鉱工業生産の数値は、製造業、鉱業、公益事業の出力を示しており、これらのセクターの活動の活性度を測るのに使われます。貿易収支は国の輸出と輸入の差額を表し、国際貿易のバランスの状態を示します。 これらの経済指標は、特に政府や中央銀行が金融政策や財政政策を決定する際に重要な役割を果たします。例えば、インフレ率が高い場合、金利を引き上げることが検討されるかもしれません。また、高い失業率は、政府による追加の景気刺激策の可能性を示唆します。経済指標を理解し分析することで、投資家や政策立案者はより情報に基づいた意思決定が可能になり、リスクを管理し、戦略を調整することができます。
消費者物価指数(CPI)
消費者物価指数はCPI(Consumer Price Index)とも呼ばれ、小売価格(末端価格)の変動を示す指数。 各国で算出方法などに多少の違いはあるものの、毎月発表され、中央銀行の政策判断・利上げ判断などの参考にもされている。 小売価格には時期により大きく変動する分野も存在するため、それらの影響を取り除いた指数も発表されている。例えば日本では生鮮食品を除いた指数を「コアCPI」、酒類を除く食品およびエネルギーを除いた「コアコアCPI」が発表されている。
日銀短観
「全国企業短期経済観測調査」。 統計法に基づいて日本銀行が行う統計調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営に資することが目的。 全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施。 短観では、企業が自社の業況や経済環境の現状・先行きについてどうみているか、といった項目に加え、売上高や収益、設備投資額といった事業計画の実績・予測値など、企業活動全般にわたる項目について調査している。
ISM製造業景況感指数
ISM製造業景気指数とは、アメリカの製造業の現在の景気の状態の印象を示す指標。これは米供給管理協会(Institute for Supply Management)がアメリカ国内の300社以上の製造業にアンケートを実施し、公表しているものである。アメリカはGDPランキングにおいて1位の国であり世界の経済動向を反映しやすい点と、毎月第一営業日にこの指標は発表されるのでほかの指標に比べて速報性がある点で、この指標は有用であるとされている。具体的には「生産」、「新規受注」、「在庫」、「価格」、「雇用」などの項目について、前月と比較し結果をスコアで表す。50が景気判断の分岐点となっており、50を上回ると製造業の景況が良く、50を下回ると悪化していることを示している。
インフレーション
インフレーションとは、物価全体が持続的に上昇し、その結果、通貨の購買力が低下する現象です。経済活動が活発になり、需要が供給を上回ると価格が上昇しやすくなります。また、生産に必要な原材料費や人件費の上昇が企業のコストに転嫁されることで、さらに物価が上昇することがあります。適度なインフレーションは経済成長の一側面とされる一方、過度な物価上昇は家計の負担を増大させ、経済全体の安定性を損なうリスクがあるため、中央銀行は金利操作などの金融政策を通じてインフレーションの抑制に努めています。