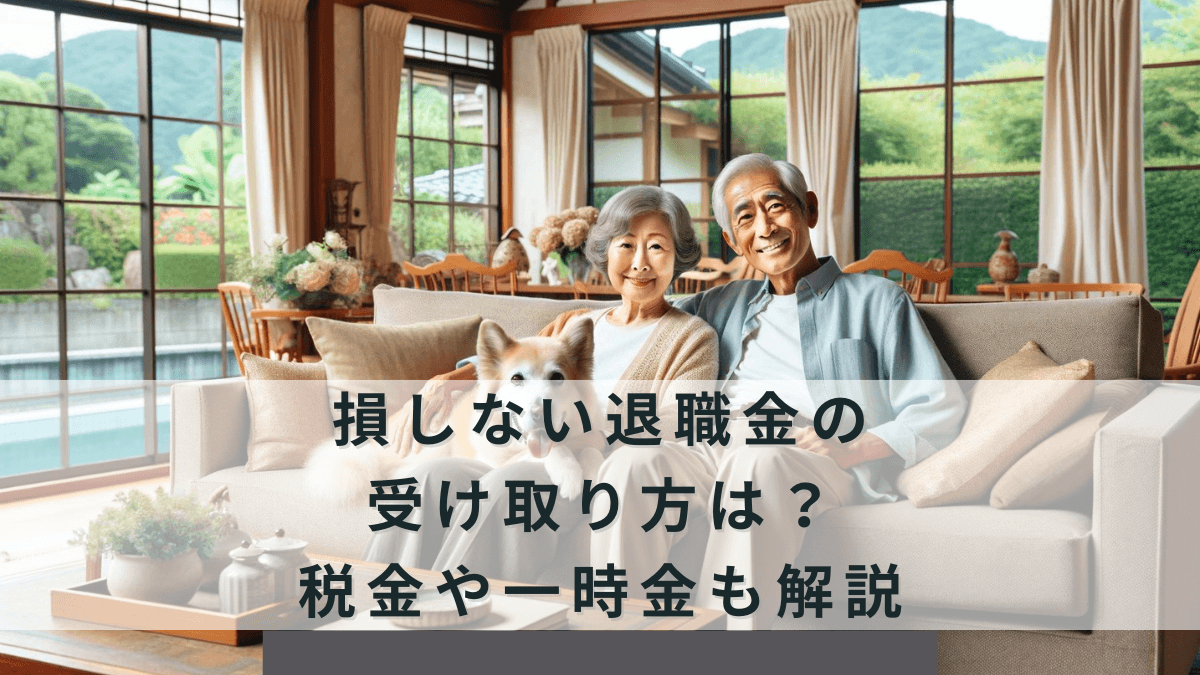企業型DCで運用している資産は退職後にどのように管理すべきですか?
男性
/ 50代
解決済み
0
2024/07/31 18:11
会社勤めをしており、企業型DCをつみたてていました。この度早期退職をすることになりましたが、まだ企業型DCの受取年齢ではないため今後も運用をしようと考えています。企業型DCで運用している資産は退職後にどのように管理すべきですか?
投資のコンシェルジュ編集部
企業型DCの退職後の資産管理方法は、年齢によって異なります。
ご相談者様は60歳未満だと考えられますので、その想定でお答えします。退職後に転職される場合、転職先企業にDC制度があれば移管、退職後転職されないもしくは、転職先企業DCの制度がない場合にはiDeCoへの移管をお勧めします。運用可能商品は転職先企業やどの証券会社でiDeCoを開設するかによって異なります。
また、退職から6ヶ月以内に移管手続きを取らないと、国民年金基金連合会へ自動移管されます。この場合掛け金の拠出、資産の運用ができない一方で、管理手数料がかかる、というデメリットがあります。必ず6ヶ月以内に手続きを行うようにしましょう。
なお、60歳以降の退職の場合は、企業型DCの運用指図者となり、老齢給付金の受取手続きができます。運用指図者とは、積立を行わず、運用のみを行う人のことです。退職までに積み立てた金額以上に掛け金を投じて積立金を増やすことはできませんが、運用は行うことが可能です。切り崩し始めるまで運用することで資産寿命を伸ばすことも可能です。
どの選択肢を取るか決定する際には、将来の資金ニーズや税制優遇の観点から、自身の状況に最適な方法を選ぶことが推奨されます。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
確定拠出年金
確定拠出年金(Defined Contribution)とは、受給者自身が資産を運用する年金制度で、個人型と企業型に分けることができる。受給者は、自らや企業が搬入した掛け金を運用し、受給要件を満たした際に給付金を受け取ることができる。給付額はそれぞれの運用法によって異なるので、老後の給付額は現役時代には確定しない。 受給者に対するメリットとしては、確定拠出年金(DC)は確定給付年金(DB)と比べて受給権が確立されていることや、自身のDC資産のみを管理すればいいことが挙げられるが、価格変動が生じるため給付額が見込みでしか計算できないというデメリットがある。
確定給付企業年金 (DB)
確定給付型企業年金(DB)とは、企業が従業員の退職後に受け取る年金額を保証する企業年金制度です。あらかじめ決められた給付額が支払われるため、従業員にとっては将来の見通しが立てやすいのが特徴です。DBには規約型と基金型の2種類があります。規約型は、企業が生命保険会社や信託銀行などの受託機関と契約し、受託機関が年金資産の管理や給付を行う仕組みです。基金型は、企業が企業年金基金を設立し、その基金が資産を運用し、従業員に年金を給付する仕組みです。確定拠出年金(DC)との大きな違いは、DBでは企業が運用リスクを負担する点であり、運用成績にかかわらず従業員は決まった額の年金を受け取ることができます。一方、DCでは従業員自身が運用を行い、将来受け取る年金額は運用成績によって変動します。DBのメリットとして、従業員は退職後の給付額が確定しているため安心感があることが挙げられます。また、企業にとっては従業員の定着率向上につながる点も利点となります。しかし、企業側には年金資産の運用成績が悪化した場合に追加の負担が発生するリスクがあるため、財務的な影響を考慮する必要があります。