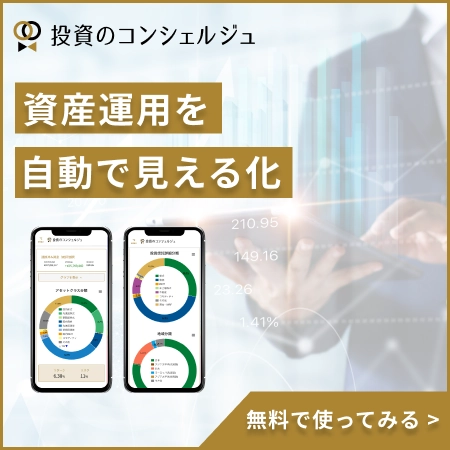相続における「遺留分」制度の解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.04.04
更新:
2025.04.04
「遺留分」は、相続の際に特定の相続人へ最低限保障される取り分です。しかし、遺言で財産を全額特定の相続人や第三者に配分した場合でも、この遺留分は守られる仕組みがあります。本記事では、遺留分の基本的な仕組みから、遺言との関係、遺留分侵害額請求の実務、さらには遺留分トラブルを未然に防ぐ事前対策まで徹底解説します。相続対策を考える資産家・地主の方は、必読の内容です。
サクッとわかる!簡単要約
この記事を読むことで、遺留分の基本的な仕組みと、相続トラブルを防ぐための具体的な対策が理解できます。遺言で自由に財産を配分しても、配偶者や子ども、親には最低限の取り分(遺留分)が保障されていることが明確になります。また、遺留分侵害額請求への対応方法として、金銭補填の手続きや、事前放棄、生命保険の活用、経営承継円滑化法の特例などの有効な対策も把握できます。さらに、遺言作成時に相続人への説明や付言事項を活用することで、相続トラブルのリスクを大幅に減らせることも理解できるでしょう。特に資産家・地主の方にとって、円満な相続と資産承継を実現するための有益な情報が得られる内容です。
1.遺留分とは何か? ── 相続人を守るための制度
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子どもなど特定の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。遺留分制度は、残された家族の生活保障や相続人間の公平を図る目的で設けられており、被相続人が遺言で自由に財産を配分した場合でも、一定の近親者には法律上確保される取り分がある仕組みです。
例えば、遺言によって特定の相続人に財産を集中させたり、第三者に全財産を譲ると指定した場合でも、配偶者や子などの遺留分権利者は自らの遺留分を主張して取り戻す権利を持ちます。
遺留分の権利を持つ法定相続人は配偶者、子(直系卑属)、および親(直系尊属)に限られます。兄弟姉妹には遺留分が認められていません。これは、兄弟姉妹は配偶者や子と異なり、通常は被相続人に経済的に依存していないためです。
遺留分の割合は、基本的には法定相続分の半分(50%)です。つまり、亡くなった人に子どもや配偶者がいる場合は、全体の遺産のうち半分は最低限、相続人に渡さなければならないというルールがあります。ただし、相続人が親(直系尊属)だけの場合は、遺留分の割合が少なくなり、全体の3分の1(約33%)になります。
たとえば配偶者と子どもが相続人であるケースでは、配偶者と子どもそれぞれ遺産全体の4分の1ずつが遺留分として確保される計算になります。このように遺留分は近親者に最低限保障された取り分であり、被相続人が遺言等でその人たちの取り分をゼロにすることはできない仕組みになっています。
2. 遺言と遺留分 ── 遺言の内容がすべてではない
一般的に「遺言を書けば自分の思い通りに財産分配できる」と考えられがちですが、遺言の内容がすべてその通りに実現するとは限りません。遺留分権利者(配偶者や子など保護された相続人)がいる場合、たとえ遺言であっても遺留分を侵害する部分については法律上優先的に修正が加えられるからです。
実際、民法では「遺言書よりも遺留分が優先される」旨が定められており、遺留分を侵害する内容の遺言はその部分について効力が否定されることになります。例えば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と指定していた場合でも、他の相続人である長女や配偶者は自分の遺留分を請求でき、その請求が認められれば遺言の指定にかかわらず遺産の一部を取り戻すことができます。
遺留分権利者が遺留分を主張すると、その侵害された分については遺言通りの分配を強制できなくなり、遺留分相当額を権利者に渡す必要があります。言い換えれば、遺言による自由な財産処分にも一定の限界があり、特に富裕層の方が特定の相続人に偏った遺産配分を考えている場合には注意が必要です。遺留分を無視した遺言を残すと、結果的に相続開始後に遺留分請求という形で争いが生じ、遺言で意図した通りの分配ができなくなるリスクが高まります。
そのため、円満な相続を実現するには、遺言作成時にあらかじめ各遺留分権利者の最低取り分を考慮し、必要に応じて遺留分に配慮した遺産配分を検討することが大切です。また、遺言書には付言事項(メッセージ)を残して自身の考えや理由を伝えておくことで、相続人が遺留分を行使するかどうかの判断に影響を与え、争いを抑止できる可能性もあります。
3. 「全額寄付」でも遺留分は守られる
遺言によって「財産の全額を慈善団体に寄付する」「第三者に全て譲渡する」といった指定をした場合でも、遺留分権利者の取り分は法律上守られます。たとえ全額を寄付しても遺留分を奪うことはできないため、相続人である配偶者や子どもは遺留分相当額を寄付先などから取り戻す権利があります。実際、民法では遺留分の請求対象に遺言による贈与(遺贈)だけでなく、生前の贈与の一部も含まれると規定されています。これは、被相続人が生前に自分の財産を大幅に減らしてしまうことで遺留分権利者の取り分がなくなる事態を防ぐためです。
具体的には、被相続人が亡くなる直前に行った多額の贈与や、明らかに遺留分権利者に不利益を与えることを意図した贈与については、その財産も相続財産に加算して遺留分を計算する仕組みになっています。
たとえば、死亡の1年前に多額の現金を第三者へ贈与していた場合、その贈与分も含めて遺産総額を算出し直し、遺留分の算定基礎に組み入れられます(民法1044条)。このため、生前に財産を処分すれば遺留分対策になるという考えは不十分であり、特に直前の寄付や贈与では効果が限定的です。
富裕層の中には社会貢献のため全財産寄付を検討される方もいますが、遺留分について事前に家族と合意しておくか、別途対策を講じない限り、遺留分権利者が後から取り分を主張する可能性がある点に留意が必要です。
4.遺留分侵害額請求の方法と実務
遺留分権利者の権利行使(=遺留分侵害額請求)とは、自分の遺留分が侵害されている場合に、不足分の金銭補填を求める手続きです。2019年の法改正以降、遺留分の請求は金銭債権として行う方式に統一されました。
これにより、従来のように直接遺産そのものを取り戻す代わりに、侵害された遺留分相当額の金銭賠償(遺留分侵害額の支払い)を請求することになります。遺留分を侵された相続人は、侵害額に相当する金額を遺産を多く受け取った相続人や受遺者(遺言で財産を受け取った人)に対して支払うよう要求できます。
請求の手続きとしては、まず内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を行うのが一般的です。この文書で「あなたが受け取った○○の遺産のうち、○○円は私の遺留分を侵害していますので支払いを請求します」といった内容を通知します。遺留分の請求は必ずしも裁判を通じて行う必要はなく、内容証明による請求だけで法的効力が生じます。
請求を受けた側(遺産を多く受け取った相続人や受遺者)は、基本的に請求に応じて支払う義務があります。遺留分は法律上保障された権利であるため、正当な請求を拒否することはできず、応じない場合は最終的に訴訟に発展し強制執行される可能性があります。
特に富裕層の相続では遺産額が大きいため、遺留分侵害額も高額になりがちであり、争いが深刻化しやすい点に注意が必要です。手続き面で重要なのは請求期限(時効)です。遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
たとえば、遺言の内容を知り自分の取り分が遺留分を下回っていると判明した日から1年以内に請求しないと、権利が消滅してしまいます(民法1048条)。また、相続開始から10年が経過すると、そもそも遺留分請求権自体が行使できなくなります(除斥期間)。したがって、遺留分が侵害されている可能性に気づいたら速やかに専門家に相談し、必要であれば期限内に適切な請求手続きを取ることが肝要です。
実務上、遺留分の請求がなされた場合の解決方法は金銭の支払いによる解決が原則です。先述のとおり現行法では金銭賠償請求権となっているため、請求を受けた側は現金や預金等で不足額を支払うことで遺留分問題を解決できます。
たとえば、ある相続人が事業用不動産を相続した結果他の相続人の遺留分を侵害していたような場合、その不動産自体を分割するのではなく、評価額に見合う金銭を支払って調整することになります。もし受遺者や他の相続人が遺産の一部を既に処分していて現物で返還できない場合でも、侵害額に相当する賠償金を支払えば遺留分請求に応じたことになり、現物の返還を拒むことが可能です。このように最終的には金銭で清算する形になるため、遺留分請求への対応には十分な流動資金の確保が重要となります。
5.遺留分への事前対策
相続開始後の遺留分請求は紛争に発展しやすく、特に資産家・富裕層の相続では遺産規模が大きく複雑なため慎重な事前対策が求められます。
資産家の場合、自社株式や不動産など分割しにくい資産が遺産に占める割合が高く、遺留分を巡る争いが生じると事業承継や資産管理に深刻な影響が及ぶ可能性があります。そこで、遺留分を巡るトラブルを未然に防ぎ、被相続人の意思をできるだけ実現するために、以下のような事前対策を検討することが有効です。
遺留分の事前放棄
相続開始前に、推定相続人に自分の遺留分を放棄してもらう方法です。遺留分権利者自身が家庭裁判所に申し立て、裁判所の許可を得られれば有効な放棄が可能となります。ただし許可には厳しい条件が課されており、単に「放棄したい」という意思だけでは認められません。裁判所は放棄の必要性・合理性があるか、放棄する人が代償として何らかの十分な利益(見返り)を得ているか等を重視します。
たとえば事業承継で後継者以外の子に十分な財産を生前贈与して生活保障した上で放棄の許可を求めるケースなどが考えられます。遺留分の事前放棄はハードルが高いものの、条件が整えば家庭裁判所の許可により法的に遺留分請求ができない状態を作ることができます。
事業承継円滑化法の特例(除外合意・固定合意)の活用
自社株式など事業用資産をお持ちの富裕層で、特定の後継者にそれら資産を集中して承継させたい場合には、「中小企業における経営承継円滑化法」に基づく遺留分に関する民法特例を活用する方法があります。
これは、全ての遺留分権利者の合意を得て家庭裁判所の許可を受けることで、指定した事業用財産を遺留分の計算の基礎から除外したり、その評価額を固定したりできる制度です。例えばオーナー社長が「自社株の全部を長男に継がせたい」という場合に、妻や他の子など遺留分権利者全員がそれに同意すれば、株式を遺留分算定から除外する合意を結ぶことができます。この特例により、後継者は事業用資産を集中承継しやすくなり、他の相続人も遺留分を主張しない(できない)ため、事業承継を円滑に進めることが可能となります。ただし全員の合意と行政(経済産業大臣)及び裁判所の認定・許可が必要であり、実現には手間と調整が伴います。
生命保険の活用(代償資金の準備)
遺留分対策として生命保険金で紛争を解決する資金を用意しておく方法も有効です。生命保険金は受取人固有の財産であり相続財産に含まれないため、例えば後継者となる長男を受取人とする保険に加入し、他の相続人の遺留分相当額を保険金で支払えるようにしておくことができます。実際に遺言書で「長男に全株式を相続させる」と定める場合、他の相続人の遺留分を侵害する恐れがありますが、被相続人が生前に長男を受取人とする生命保険に加入し、長男が保険金で遺留分相当額(代償交付金)を用意できるようにしておけば、長男はその保険金を使って他の相続人に支払うことで遺留分請求に対応できます。
こうした代償資金の準備により、主たる相続財産(例えば自社株や不動産)を手放すことなく遺留分の問題を解決し、相続人間の争いを緩和することが期待できます。なお、生命保険金は相続税法上「みなし相続財産」として一定額が非課税枠となるメリットもあるため、遺留分対策と節税効果の両面から検討する価値があります。
遺言書での配慮と生前のコミュニケーション
遺留分を巡る紛争を防ぐ最も基本的な対策は、遺留分権利者に十分配慮した遺言内容を心がけることです。各相続人の遺留分を侵さない範囲で遺産配分を決めておけば、相続人は遺留分請求をする動機自体がなくなるため、争いを未然に防げます。また、遺言書に付言事項として「なぜそのような分配にしたのか」「各相続人へどのような思いがあるのか」を丁寧に記すことで、仮に法定相続分との差があっても納得感を高め、遺留分請求を思いとどまらせる効果が期待できます。
さらに、可能であれば生前に家族と財産承継について話し合っておくことも有効です。被相続人が存命中に自分の考えを率直に伝え、相続人間で理解と合意を得ておけば、相続開始後に「こんな遺言は聞いていない」「不公平だ」といった感情的対立を避けることができます。
ただし富裕層の中には「生前に財産の詳細を家族に知られたくない」という方もいるため、その場合でも専門家を交えて遺留分対策のシミュレーションを行い、遺言内容に反映させるなど間接的なコミュニケーションを図るとよいでしょう。重要なのは、被相続人の意思と相続人の納得のバランスを事前に調整しておくことです。
以上のように、遺留分制度は相続人の最低限の権利を守る反面、富裕層の相続においては遺産分割の柔軟性を制約し紛争の火種にもなり得るものです。だからこそ、遺留分への対策は早めに検討しておき、専門家の助言を得ながら円満で計画的な資産承継を実現することが大切です。遺留分制度を正しく理解し上手に対応することで、ご自身の望む相続の形とご家族の幸せの双方を守ることにつながるでしょう。
この記事のまとめ
遺留分制度は、相続人の権利を守る一方で、特定の相続人への財産集中を難しくする要因にもなります。特に、不動産や自社株の相続を考えている方にとって、遺留分侵害額請求への対応策を講じておかないと、将来的に相続トラブルに発展する可能性があります。
また、事前放棄や経営承継円滑化法の特例など、専門知識が必要な対策は、法律・税務の専門家と相談しながら進めることが重要です。さらに、生命保険の活用や家族信託など、柔軟な相続対策を行うことで、スムーズな資産承継が実現できます。
相続対策は早めの準備が肝心です。専門家と共に、最適な遺留分対策を検討してみませんか?

MONO Investment
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
投資のコンシェルジュ編集部は、投資銀行やアセットマネジメント会社の出身者、税理士など「金融のプロフェッショナル」が執筆・監修しています。 販売会社とは利害関係がないため、主に個人の資産運用に必要な情報を、正確にわかりやすく、中立性をもってコンテンツを作成しています。
関連質問
関連する専門用語
遺留分
遺留分とは、被相続人が遺言などによって自由に処分できる財産のうち、一定の相続人に保障される最低限の取り分を指す。日本の民法では、配偶者や子、直系尊属(親)などの法定相続人に対して遺留分が認められており、兄弟姉妹には認められていない。遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」によって不足分の金銭的補填を請求できる。これは相続財産の公平な分配を確保し、特定の相続人が極端に不利にならないようにするための制度である。
法定相続人
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことを指します。被相続人が亡くなった際に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などが法律上の順位に従って財産を相続する権利を持ちます。配偶者は常に相続人となり、子がいない場合は直系尊属(親や祖父母)、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。相続税の基礎控除額の計算や遺産分割の際に重要な概念であり、相続対策を検討する上で欠かせない要素となります。
被相続人
被相続人とは、亡くなったことにより、その人の財産や権利義務が他の人に引き継がれる対象となる人のことです。つまり、相続が発生したときに、その資産の元々の持ち主だった人を指します。たとえば、父親が亡くなって子どもたちが財産を受け継ぐ場合、その父親が「被相続人」となります。相続は被相続人の死亡と同時に始まり、相続人は法律や遺言の内容にしたがって財産を引き継ぎます。資産運用や相続対策を考える際、この「被相続人」という概念はすべての出発点となる重要な言葉です。
生命保険
生命保険とは、契約者が一定の保険料を支払うことで、被保険者が死亡または高度障害になった際に保険金が支払われる仕組みのことです。主に遺族の生活保障を目的とし、定期保険や終身保険などの種類があります。また、貯蓄性を備えた商品もあり、満期時に保険金を受け取れるものもあります。加入時の年齢や健康状態によって保険料が異なり、長期的な資産運用やリスク管理の一環として活用されます。
相続税
亡くなられた親などから、お金や土地などの財産を受け継いだ(相続した)場合に、その受け取った財産にかかる税金。
遺留分権利者
遺留分権利者とは、法律で定められた「最低限の相続分」である遺留分を受け取る権利を持っている相続人のことを指します。たとえば、亡くなった方が遺言で全財産を特定の相続人や第三者に渡すと記した場合でも、遺留分権利者には一定の取り分を請求する権利があります。 具体的には、配偶者、子ども、直系尊属(両親や祖父母など)が遺留分権利者に該当し、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。この制度は、相続における公平性を保ち、特定の相続人だけが極端に不利になるのを防ぐために設けられています。遺言によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」という手続きによって、他の受益者に対して金銭で補償を求めることができます。資産の分配を公平に行うためにも、遺留分とそれを主張できる遺留分権利者の存在は、相続対策において非常に重要なポイントです。
遺言
遺言とは、自分が亡くなったあとに財産をどのように分けるかや、誰に何を遺すかなど、自分の最終的な意思を文書として残すものです。遺言を書くことで、遺産の分け方を自分の意志で決めることができ、相続人同士の争いを未然に防ぐことにもつながります。 遺言には、自筆で全文を書く「自筆証書遺言」、公証人が関与して作成される「公正証書遺言」、特別な状況で認められる「秘密証書遺言」などいくつかの形式があり、それぞれ法的なルールに従って作成する必要があります。法的に有効な遺言があれば、その内容は相続において優先されます。資産運用や相続計画において、遺言は自分の思いを形にし、家族に円滑に財産を引き継がせるためのとても大切な手段です。
直系卑属
直系卑属とは、自分から見て「直接下の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。たとえば、自分の子どもや孫、ひ孫などがこれに該当します。逆に、甥や姪、いとこなどは直系ではないため、直系卑属には含まれません。 法律や相続の分野では、直系卑属がいるかどうかによって、相続の順位や税金の取り扱いが大きく変わります。たとえば、贈与税には「直系卑属への贈与」であれば、特例として税率が軽減されたり、非課税枠が広がったりする制度があります。また、遺言書を作成する際にも、直系卑属への配慮が重要視されることが多く、財産の引き継ぎにおける中心的な存在です。資産運用や相続対策を行ううえでは、この「直系卑属」という概念を正しく理解しておくことが非常に重要です。
直系尊属
直系尊属とは、自分から見て「直接上の世代」にあたる血縁関係のある人を指します。具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などがこれに該当します。たとえば、自分の親や祖父母はすべて直系尊属ですが、叔父や伯父、兄姉などは含まれません。 法律や相続の分野では、この「直系尊属」という関係性が非常に重要です。たとえば、相続税の計算や贈与税の特例などで、直系尊属からの贈与であれば税金が軽くなる制度が用意されていることがあります。また、法定相続の順位や扶養義務などでも、直系尊属であるかどうかが判断の基準になることがあります。資産運用や相続対策を考えるうえで、家族の中の関係性を正確に理解することが大切であり、その基本となるのがこの直系尊属という考え方です。
遺贈
遺贈とは、遺言書によって自分の財産を相続人や第三者に無償で譲ることを指します。生前の贈与とは異なり、遺贈は本人が亡くなったときに初めて効力が生じるのが特徴です。たとえば、「私の預金を○○さんに渡す」といった内容を遺言書に書いておけば、その人が相続人であってもなくても、遺贈として財産を受け取ることができます。 遺贈は、特定の財産を指定して渡す「特定遺贈」と、財産の一定割合を指定して渡す「包括遺贈」に分けられます。また、相続人以外の人や団体(たとえば知人や慈善団体など)にも遺贈することが可能なため、本人の意思を柔軟に反映できる方法として活用されています。資産運用や相続の場面では、誰にどの財産をどのように渡すかを明確にする手段として、遺贈はとても大切な制度です。
生前贈与
生前贈与とは、本人が亡くなる前に、自分の財産を家族や親族などに贈り与えることを指します。たとえば、子どもや孫に現金や不動産などを自分の意思で生きているうちに渡す行為がこれにあたります。生前贈与を活用することで、相続時に財産が一度に多額に移転するのを防ぎ、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。ただし、贈与にも贈与税がかかるため、贈与額やタイミング、誰に贈るかによって課税額が大きく変わることがあります。また、一定の条件を満たせば非課税になる特例制度もあるため、計画的に行うことが重要です。資産運用や相続対策として、生前贈与は家族に財産を無理なく引き継がせるための有効な手段のひとつです。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、相続人の最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」を侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める手続きのことを指します。たとえば、遺言によって特定の相続人だけに多くの財産が渡され、他の相続人が本来もらえるはずの遺留分を受け取れなかったときに、侵害された相続人が他の相続人や受遺者に対してその差額を金銭で請求することができます。 この制度は、相続人間の不公平を防ぎ、一定の相続権を保護するために設けられています。2019年の民法改正により、かつては「遺留分減殺請求」として行われていたものが、現在は金銭による支払いを求める「遺留分侵害額請求」となりました。資産運用や相続の場面では、遺言によって財産の分け方を自由に決める一方で、遺留分という法律上の制約を理解し、トラブルを防ぐための知識として非常に重要です。
金銭賠償
金銭賠償とは、他人に損害を与えた場合に、その損害をお金で埋め合わせることを指します。たとえば、交通事故や契約違反などによって相手に損失を与えたとき、その損失を補うために一定の金額を支払うことで責任を果たすのが金銭賠償です。この賠償は、壊れた物の修理費用や治療費、慰謝料など、さまざまな損害に対応して支払われることがあります。法的な手続きや裁判を通じて請求されることも多く、個人間だけでなく、企業や相続の場面でも発生することがあります。資産運用の観点では、予期せぬ金銭賠償が発生するリスクに備えて保険を活用することや、相続財産に含まれる賠償責任を把握することが重要です。
受遺者
受遺者とは、遺言書によって財産を受け取ることが指定された人のことを指します。つまり、亡くなった方(遺言者)が生前に書いた遺言書の中で、「この人に財産を渡します」と明記された受取人です。受遺者は相続人である場合もあれば、相続人以外の第三者であることもあります。たとえば、「長男に不動産を渡す」「お世話になった知人に預金の一部を贈る」などと記載されていれば、その対象となる人が受遺者です。遺言による財産の受け取りは、法律で定められた相続とは別の仕組みで行われるため、遺言書の内容に従って確実に権利を得ることができます。資産を特定の人に託したいという希望を実現するために、遺言と受遺者の制度は非常に重要な役割を果たします。
除斥期間
除斥期間とは、ある権利が成立してから一定の期間が過ぎると、たとえその権利を行使しようとしなくても自動的に消滅してしまう期間のことです。似たような概念に「時効」がありますが、除斥期間は時効のように「主張しないと消えない」のではなく、期間が過ぎれば当然に効力がなくなるという点で大きく異なります。たとえば、不法行為による損害賠償請求権は、発生から20年が経過すると除斥期間により行使できなくなります。この制度は、いつまでも不確定な権利関係が残ることを防ぎ、法律上の安定性や公平性を保つために設けられています。資産運用や相続の分野でも、請求権の有効性を確認するうえで知っておくべき重要な考え方です。
経営承継円滑化法
経営承継円滑化法とは、中小企業の経営者が引退や死亡によって事業を後継者に引き継ぐ際に、その手続きを円滑に進められるよう支援することを目的とした法律です。正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といいます。経営者が亡くなった場合には、相続税や贈与税の負担が重く、事業の継続が難しくなることがあります。そこでこの法律では、相続税の納税猶予制度や、事業に必要な株式や資産をスムーズに後継者に渡すための手続きを整備しています。また、遺留分に関する民法の特例を適用することで、親族間の相続トラブルを回避しやすくする効果もあります。資産運用と同様に、企業の資産や経営権のスムーズな引き継ぎを実現するために欠かせない法律です。
付言事項
付言事項とは、遺言書の中で法律的な効力を持たないものの、遺言者の気持ちや家族へのメッセージなどを自由に書き添える部分のことです。たとえば、「これまで育ててくれてありがとう」や「仲良く助け合ってほしい」などの感謝や願いを記すことができ、相続人にとって心の支えになることもあります。また、なぜこのような遺言内容にしたのかという背景や理由を説明することも可能です。法的な拘束力はありませんが、相続人同士の誤解や争いを防ぐための重要な役割を果たすことがあります。資産だけでなく思いも一緒に引き継ぐという意味で、遺言書において非常に大切な要素です。
代償交付金
代償交付金とは、相続の際に特定の相続人が多くの財産を受け取る代わりに、他の相続人に対してその公平を保つために支払うお金のことです。たとえば、相続財産に不動産が含まれていて、それを一人の相続人が単独で取得する場合、他の相続人が何ももらえないと不公平になります。そこで、その不動産を取得した相続人が、他の相続人に対して代わりのお金(代償交付金)を支払うことで、バランスを取るのです。この方法を使えば、相続財産を売却せずに現物のまま引き継ぎながら、相続人全員の納得を得ることができます。資産運用や不動産を含む相続の場面では、円満な遺産分割を実現するための有効な手段として用いられます。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どんな内容の文書を送ったのかを、日本郵便が証明してくれる特別な郵便のことです。たとえば、お金の返済を正式に請求したり、契約の解除を通知したりする場合に使われます。普通の手紙とは違い、郵便局が内容を記録・保管し、あとから「確かにこの文書を送りました」と証明してくれるため、トラブルが起きたときに自分の主張を裏付ける証拠として使えます。資産運用や相続の場面でも、貸付金の返還請求や相続放棄の意思表示など、法的に重要なやりとりを確実に記録に残したい場合に活用されることがあります。慎重に相手に伝えたい意思があるときに、非常に役立つ手段です。