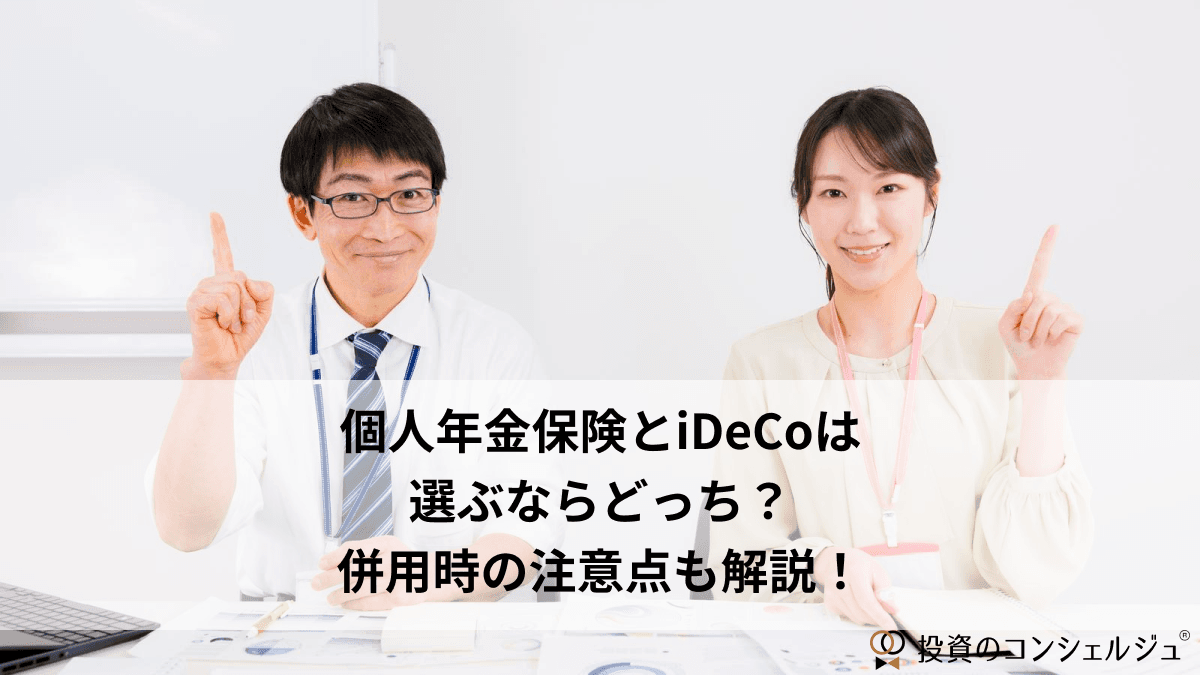iDeCoや企業型DCは転職時に移換可能?確定拠出年金のポータビリティの仕組みや手続きを解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.01.21
更新:
2025.03.18
確定拠出年金は、運用している資産の持ち運び(ポータビリティ)が可能です。昨今は転職する人が増えて雇用が流動化している関係もあり、確定拠出年金のポータビリティについて理解する重要性が高まっています。
もし運用している資産を確定拠出年金の制度内で適切に移さないと、不利益を被るため注意が必要です。
今回は、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCをはじめとした確定拠出年金のポータビリティや、損をすることなく資産を移す方法を解説します。
確定拠出年金制度の概要とポータビリティとは
確定拠出年金とは、加入者が資産運用しながら老後資産を用意する制度です。拠出された掛金と運用益の合計額をもとに、将来の給付額が決まる点が特徴です。
確定拠出年金には、事業主が行う「企業型DC」と個人が行う「iDeCo」があります。
| 企業型DC | iDeCo | |
|---|---|---|
| 実施主体 | 事業主 | 国民基金連合会 |
| 加入者 | 実施企業に勤務する従業員(基本的に社会保険加入者) | 公的年金制度加入者※ |
※国民年金保険料納付を免除されている方・老齢基礎年金を繰上受給している方・農業者年金に加入している方・企業型確定拠出年金でマッチング拠出をしている方などは加入できない
企業年金は老後のための資産形成制度になるため、転職・退職したとしても60歳になるまでは原則として受け取れません。転職・退職して勤務先の企業年金から脱退する場合は、別の制度に資産を持ち運ぶ必要があります。
確定拠出年金の制度内で資産を持ち運ぶことを「ポータビリティ」といいます。ポータビリティの仕組みにより、転職したときや働き方を変えた(会社員から自営業者になる)ときでも、確定拠出年金の資産を持ち運ぶことが可能です。
非課税で運用できる確定拠出年金制度のメリットを活かすためにも、ポータビリティの仕組みを理解することは大切です。
私的年金のポータビリティが必要となる状況
具体的に、どのような場合でポータビリティが必要になるのか解説します。
なお、年金資産の移管先が確定給付企業年金(DB)になる場合、移換先の規約で資産移換を受けることができる旨が定められていることがポータビリティの条件となります。
また、移換前の年金資産が確定給付企業年金の場合、移換する金額は脱退一時金相当額または残余財産となります。
確定給付企業年金(DB)のポータビリティ
確定給付企業年金(DB)で運用している資産は、以下の制度へのポータビリティが可能です。
| 移管先 | 想定されるケース |
|---|---|
| 企業型DC | ・企業型DCを実施している企業へ転職する場合 |
| DB | ・DBを実施している企業へ転職する場合 (他社のDB等からの移換を受け入れることができる旨が定められていること) |
| iDeCo(退職時に一時金を受け取る権利がある場合、脱退一時金相当額を移換可能) | ・企業年金がない企業へ転職する場合 ・企業年金がある企業へ転職し、あわせてiDeCoも行う場合 ・自営業者、専業主婦(夫)になる場合 |
確定給付企業年金制度を導入している企業から転職する場合、転職先の企業に企業型DCまたは確定給付企業年金の制度があれば、当該制度に資産を移せます。
この場合、転職先企業の担当者に、資産を移管する手続きを依頼しましょう。
転職先の企業にいずれの企業年金制度がない場合は、iDeCoに移して運用を行うことになります。自営業やフリーランスになる場合や、専業主婦(夫)になる場合も同様です。
この場合、iDeCoの運営管理機関を自分で選択し、機関ごとに決まっている方法で移換の手続きを進めましょう。
なお、いずれかの企業年金に加入しつつ、iDeCoへ同時に加入することも可能です。移換前のDBの資産を転職先の企業年金に移換するかiDeCoに移管するかは、任意に選択できます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)から移管する場合のポータビリティ
企業型DCのポータビリティは、確定給付企業年金とほとんど同じです。
| 移管先 | 想定されるケース |
|---|---|
| 企業型DC | ・企業型DCを実施している企業へ転職する場合 |
| DB | ・DBを実施している企業へ転職する場合(企業型DCからの移換を受け入れることができる旨が定められていること) |
| iDeCo | ・企業年金がない企業へ転職する場合 ・企業年金がある企業へ転職し、あわせてiDeCoも行う場合 ・自営業者、専業主婦(夫)になる場合 |
例えば、転職先の企業にDBまたは企業型DCの制度があれば、当該制度に資産を移せます。DBへ移す場合は、転職先の企業に企業型DCからの移換を受け入れることができる旨が、規約で定められている必要があります。
転職先の企業の担当者に、前職の企業型DCの資産を移したい旨を伝えればよいでしょう。
転職先の企業にいずれの企業年金制度がない場合や、自営業や専業主婦(夫)になる場合はiDeCoへ資産を移します。運営管理機関を自分で選択し、運営管理機関の案内に沿って移換の手続きを進めましょう。
企業年金に加入しつつiDeCoへ加入する場合、移換前の企業型DCの資産を転職先の企業年金に移すかiDeCoに移すかは、任意に選択できます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)から移管する場合のポータビリティ
iDeCoも、企業型DC・DB・iDeCoへのポータビリティに対応しています。
| ポータビリティ先 | 想定されるケース |
|---|---|
| 企業型DC | ・企業型DCを実施している企業へ転職する場合 ・勤務先が企業型DCを導入した場合 (企業型DCに加入しながらiDeCoを継続することも可能) |
| DB | ・DBを実施している企業へ転職する場合 (iDeCoからの移換を受け入れることができる旨が定められていること) |
| iDeCo | ・運営管理機関を変更する場合 |
例えば、現在の勤務先に企業年金制度がない状態でiDeCoを行っている人が、企業年金制度がある企業へ転職する場合はiDeCoの資産を企業年金に移せます。企業の担当者にiDeCoの運用資産を移したい旨を伝えましょう。
企業型DCに加入しながらiDeCoを継続する場合は、資産を移すことなく、そのままiDeCoで運用することが可能です。
企業型DCとiDeCoを併用する方法に関しては、こちらの記事をご覧ください。
参考:企業型DCとiDeCoは併用できる?仕組みと注意点を徹底解説!
確定拠出年金のポータビリティを行わない場合のデメリット
転退職をしたときは、確定拠出年金やiDeCoの資産について、ポータビリティの手続きを行う必要性が生じます。確定拠出年金に加入していた人が、退職後6カ月以内に手続きをしないと、国民年金基金連合会へ自動移換されます。
「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況」によると、2024年7月末の段階で約132万人の人が自動移換者となっているようです。
もしポータビリティを行わないと、さまざまな不利益が起こるため注意が必要です。以下で、具体的な不利益の内容を解説します。
国民年金基金連合会へ自動移管され資産運用ができなくなる
自動移換されると、一切運用ができなくなります。それまで運用していた商品はすべて売却され、ただ現金として保管されるだけなので、運用益はもちろん利息も付きません。
もし自動移換後に相場が上昇しても、運用していた投資信託は売却されているため、運用益は得られません。きちんとポータビリティの手続きをしていれば得られた運用益を逃してしまうため、もったいない事態といえるでしょう。
確定拠出年金制度やiDeCoは、運用益が非課税となる税制優遇があります。しかし、自動移換されると税制優遇を活用できないため、制度のメリットを受けられません。
様々な手数料が発生し資産が減り続ける
自動移換されると、さまざまな手数料が発生します。
| ケース | 手数料 |
|---|---|
| 自動移換されるとき | 4,348円 (国民年金基金連合会へ1,048円、 特定運営管理機関へ3,300円) |
| 自動移換されている間 | 毎月52円 |
| 企業年金やiDeCoへ移すとき | 1,100円 |
自動移換されると余計な手数料を負担することになるため、注意しましょう。「毎月52円であれば大した金額ではない」と感じるかもしれませんが、先ほどお伝えしたように自動移換されている間は一切運用ができません。
つまり、ただ年金原資が減り続けるため、もったいない状況といえるでしょう。
なお、一般的に企業年金から企業年金へ資産を移す場合は手数料がかかりません。企業年金からiDeCoへ資産を移す場合は、国民年金基金連合会へ支払う2,829円の手数料で済みます(運営管理機関によっては追加で手数料が発生)。
老齢給付金を受け取るタイミングや控除額に影響する
国民年金基金連合会に移換されると、老齢給付金を受け取るタイミングに影響が出る可能性があります。確定拠出年金やiDeCoでは、加入期間に応じて老齢給付金を受け取れる年齢が以下のように決まっているためです。
| 通算加入者等期間 | 受取開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1月以上2年未満 | 65歳 |
国民年金基金連合会に移換されている期間は「通算加入者等期間」に算入されません。
例えば、3年間企業型DCに加入したあとに転職し、ポータビリティをせずに放置していると、老齢給付金を受け取れるのは早くても64歳からです。この場合、「60歳になったら年金を受け取ろう」と考えていると、資金計画が狂ってしまうかもしれません。
また、企業年金やiDeCoを一時金で受け取る際には、受けられる退職所得控除が低くなってしまうデメリットがあります。退職所得控除は掛金を拠出した期間に基づいて計算されますが、自動移換となっている期間は掛金を拠出しないため、自動移換の期間が長いほど退職所得控除が小さくなってしまうのです。
受取時の税制優遇メリットを最大限生かせなくなってしまう点も、自動移管されるデメリットといえるでしょう。
確定拠出年金ポータビリティの手続き方法
確定拠出年金のポータビリティを怠ると、さまざまなデメリットが起こる点を解説しました。転職や退職の予定がある方は、必ずポータビリティを行いましょう。
以下で、ポータビリティの手続き方法をケース別で解説します。
企業型DCからiDeCoへ移管する場合
企業型DCからiDeCoへ年金資産を移す場合の流れは、以下のとおりです。
- 運営管理機関(金融機関や証券会社など)を選ぶ
- iDeCoの口座開設を申し込み、「個人別管理資産移換依頼書」を提出する
運営管理機関によって、取り扱っている金融商品のラインナップや手数料体系が異なります。手数料をできるだけ抑えたい場合は、ネット型の証券会社を選択するとよいでしょう。
なお、企業型DCからiDeCoへ移す必要性がある具体的な場面は、以下のとおりです。
| 第2号被保険者で いるケース | 第2号被保険者で なくなるケース |
|---|---|
| ・企業型DCのない企業に転職した ・企業型DCの対象者でなくなった ・公務員へ転職し共済組合員の資格を取得した | ・自営業者やフリーランスになった ・専業主婦(夫)になった |
第2号被保険者でなくなる場合はiDeCoへのポータビリティが必須で、第2号被保険者でいる場合(転職する場合)は「転職先に企業年金制度があるかどうか」次第で、iDeCoへのポータビリティが必要か異なります。
なお、iDeCoに資産を移したあと、掛金を拠出しないという選択も可能です。「掛金を拠出し続けて60歳以降に受け取る」あるいは「掛金の拠出は停止して、60歳以降まで運用だけ続ける」かを自由に選択できます。
企業型DCから企業型DCへ移管する場合
企業型DCがある企業から企業型DCがある企業へ転職する場合は、企業型DCの制度内で資産を移せます。転職先企業の担当者に「前職で運用していた企業年金の資産がある」旨を伝えれば、資産を移すために必要な手続きを案内してくれるでしょう。
ただし、運営管理機関ごとに取り扱っている運用商品は異なるため、転職後に運用商品を選び直す必要があります。早い段階で資料をもらい、どの商品をどの配分で購入するか決めるとよいでしょう。
iDeCoから企業型DCへ移管する場合
iDeCoから企業型DCへ年金資産を移すときには、「iDeCoをやめるか」「iDeCoを継続するか」によって手続きが異なります。
| 就職先・転職先の 企業年金 | ポータビリティの内容 |
|---|---|
| 企業型DCがある | 【iDeCoと同時加入しない場合(いずれか選択)】 ・年金資産をiDeCoから企業型DCへ移換する ・iDeCoの運用指図者となり、iDeCoの掛金は拠出せずに運用だけ行う 【iDeCoと同時加入する場合(いずれか選択】 ・年金資産をiDeCoから企業型DCへ移換する ・引き続きiDeCoの加入者のままでいる |
| 企業型DCがない | 引き続きiDeCoの加入者となる |
iDeCoをやめる場合は、iDeCoの個人別管理資産を就職先の企業型DCに移す必要があります。iDeCoの運営管理機関に「加入者資格喪失届」を提出したうえで、就職先企業の担当者に手続きの流れを確認しましょう。
就職先の企業で企業型DCに加入しつつ、iDeCoを継続することも可能です。第2号被保険者以外から第2号被保険者に新しく該当する場合、「加入者被保険者種別変更届」と「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (就職先の証明が必要)」を運営管理機関へ提出する必要があります。
第2号被保険者の種別が変わらない場合は、「加入者登録事業所変更届 」と「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 (就職先の証明が必要)」を運営管理機関へ提出しましょう。
なお、iDeCoから企業型DCへ資産を移す必要性がある具体的な場面は、以下のとおりです(いずれもiDeCoをやめる場合)。
- 自営業者や学生としてiDeCoに加入していた人が、企業型DCの制度がある企業へ就職した
- 勤務先の企業型DCがなくiDeCoに加入していた人が、企業型DCの制度が新しく設けられた
- 勤務先の企業型DCがなくiDeCoに加入していた人が、企業型DCのある企業へ転職した
転職するときや働き方が変わるときは何らかの手続きが必要となるため、自分の状況に合わせてやるべきことを確認しましょう。
確定拠出年金ポータビリティに関する注意点
自動移換されるとさまざまなデメリットがあるため、ポータビリティの手続きは必ず行いましょう。以下で、ポータビリティに関する注意点を解説します。
退職後6カ月以内に手続きを行う
退職後6カ月以内にポータビリティの手続きを行わないと、自動移換されます。転退職後は何かと忙しく手続きを放置してしまいがちですが、期限を厳守しましょう。
ただし、昨今は自動移換者を減らすための取り組みが行われています。自動移換の状態で新たにiDeCoの加入者になったことが確認できた方は、ポータビリティの手続きをしなくても、iDeCoへ資産を移す処理が行われるようになりました。
ポータビリティ利用後に運用商品を選び直す必要がある
企業型DCやiDeCoでは、運営管理機関ごとに取り扱っている運用商品が異なります。ポータビリティの手続きを済ませたあとは、新しい制度でどの運用商品に投資するか決めなければなりません。
購入する商品を決定しないと、自動的に元本確保型商品を購入する設定になります。積極的に運用したいと考えている方は、早い段階で運用商品を決定しましょう。
国民年金基金連合会に自動移換された場合の対応策や手続き
もし確定拠出年金の資産が自動移換されたら、状況に応じて以下の中から必要な手続きを行いましょう。
- 勤務先の企業型DCまたはDBに移す
- iDeCoに移す(運用指図者になる場合も含む)
- 脱退一時金を受け取る
なお、脱退一時金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります
- 60歳到達前に企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失している
- 企業型DC・iDeCo加入者または運用指図者でない
- 喪失した月の翌月から6ヶ月が経過していない
- 個人別管理資産額が15,000円以下である
勤務先に企業年金制度がある場合、速やかに自動移換となっている資産を移しましょう。企業の担当者に問い合わせれば、必要な手続きを教えてもらえます。
勤務先に企業年金制度がない場合や自営業者の方は、iDeCoの口座を開設しましょう。掛金を拠出しながら運用を行うケースと、掛金を拠出せずに運用だけ行う「運用指図者」になるケースに分かれます。
年齢や年金保険料の納付状況によって、運用を行えるかどうかが異なるため、詳細は口座開設を検討している運営管理機関に問い合わせましょう。
なお、自動移換されたときと自動移換となり手続きを放置している期間中は、国民年金基金連合会から書類が届きます。国民年金基金連合会から書類が届いたら、必ず中身を確認して自動移換となっていないか確認しましょう。
まとめ
転職したときや働き方が変わったとき(会社員や公務員へなるとき、会社員から自営業者になるときなど)は、確定拠出年金の資産を移す必要があります。ポータビリティの手続きを怠ると自動移換されてしまい、さまざまなデメリットを被る点に注意しましょう。
非課税で運用できるメリットを活用できないだけでなく、毎月手数料がかかり続けるため大切な資産が減ってしまいます。自動移換されるメリットは何もないため、ポータビリティの手続きは必ず行うべきです。
手続きにあたって不安がある場合は、転職先の企業や国民年金基金連合会、運営管理機関(iDeCoの口座開設を予定している金融機関)に確認するのがおすすめです。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
国民年金基金連合会
国民年金基金連合会は、国民年金法に基づき設立された公的な年金制度であり、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。 国民年金基金連合会は、転居や転職により基金の加入員資格を喪失した中途脱退者に対して、年金や遺族一時金の支給を行っています。また、平成14年からは確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、規約の作成や掛け金の収納業務なども行っています。 退職等により加入していた企業型DCを脱退し、6ヶ月以上移管の手続きを行わなかった場合、国民年金基金連合会に自動的に移管されます。その場合、現金で保管されるため追加の積立や運用指図を行うことができず、さらに移管時と保管時に手数料がかかります。
確定拠出年金
確定拠出年金(Defined Contribution)とは、受給者自身が資産を運用する年金制度で、個人型と企業型に分けることができる。受給者は、自らや企業が搬入した掛け金を運用し、受給要件を満たした際に給付金を受け取ることができる。給付額はそれぞれの運用法によって異なるので、老後の給付額は現役時代には確定しない。 受給者に対するメリットとしては、確定拠出年金(DC)は確定給付年金(DB)と比べて受給権が確立されていることや、自身のDC資産のみを管理すればいいことが挙げられるが、価格変動が生じるため給付額が見込みでしか計算できないというデメリットがある。