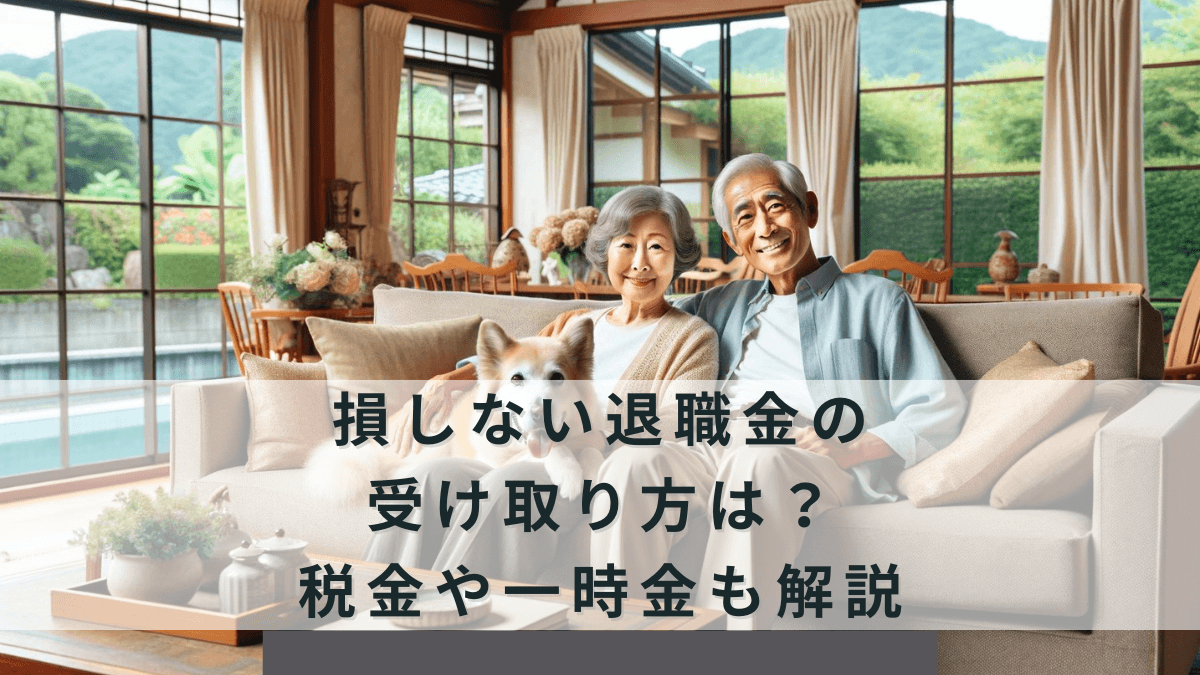年金の課税はいくらから?年金所得と公的年金控除の仕組みや計算方法を解説
難易度:
執筆者:
公開:
2025.01.07
更新:
2025.03.29
年金を受給している方やこれから受給予定の方は、年金所得の課税ルールや計算方法について知っておくとよいでしょう。なお、「年金所得」とは俗称で、所得税法上は雑所得と呼びます。
最終的に、年金受給者が自由に使えるお金は手取り額である以上、どのような計算式で税額が決まるのか把握することは大切です。
今回は、年金受け取りに関する税金や公的年金控除の仕組みなどを解説します。
日本の年金の種類

年金には大きく分けて「公的年金」と「私的年金」があります。
1階部分の国民年金(基礎年金)は、20歳以上60歳未満の方が必ず加入する公的年金です。2階部分の厚生年金は会社員や公務員が加入する公的年金ですが、厚生年金に加入しない自営業者や学生、専業主婦(夫)などは私的年金である国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)で備えられます。
さらに、国民年金と厚生年金の上乗せとして私的年金に加入したり、複数の私的年金を活用すれば3階部分の年金を作れます。以下で、それぞれにどのような年金制度があるのか確認しましょう。
公的年金制度:国民年金と厚生年金など特定条件で加入必須な年金
日本の公的年金制度は以下の2種類です。
- 国民年金:20歳以上60歳未満のすべての方が加入する
- 厚生年金:会社員・公務員の方が加入する
専業主婦や学生、自営業者の方は国民年金のみ加入しますが、会社員・公務員の方は国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入します。
私的年金:公的年金に上乗せする任意加入の年金
私的年金とは、公的年金の上乗せとなる年金です。公的年金は条件を満たせば強制的に加入しますが、私的年金は勤務先の制度や個人の判断次第となるため、全員が加入するとは限りません。
| 年金 | 説明 |
|---|---|
| 確定給付企業年金(DB) | 確定給付企業年金制度を導入している企業に勤めている方のみ利用できる |
| 企業型確定拠出年金(企業型DC) | 企業型確定拠出年金制度を導入している企業に勤めている方のみ利用できる |
| 個人型確定拠出年金(iDeCo) | 国民年金制度加入者は利用できる(国民年金保険料の免除または猶予を受けている方、企業型確定拠出年金加入者でマッチング拠出を選択していないなど、例外あり) |
| 国民年金基金 | 第1号被保険者や国民年金の任意加入者が利用できる |
| 個人年金保険 | 生命保険会社によって加入できる年齢は異なる |
例えば、確定給付企業年金(DB)や企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入できるかどうかは勤務先次第です。制度の有無や加入対象者の範囲が企業ごとに異なります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)や個人年金保険は、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金よりも加入できる範囲が広いという特徴があります。加入する際の窓口となるのは、金融機関や保険会社です。
年金はいくらから課税される?実は雑所得な年金の課税関係
受け取る年金は「年金所得」という俗称で呼ばれることもありますが、所得税法上は「雑所得」に該当します。
課税対象となる年金の計算式は「年金の総額-公的年金控除」です。雑所得は総合課税となるため、年金以外の雑所得や雑所得以外の課税対象を含めて、所得税率を乗じれば所得税額を計算できます。
例えば、65歳以上で年金額が200万円の方が受けられる公的年金等控除は110万円です。
なお、源泉徴収される税額は、年金額から公的年金等控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額で一定です。
公的年金から税金が源泉徴収される基準は、以下のとおりです(障害年金と遺族年金は非課税)。
- 65歳未満の方:108万円を超える
- 65歳以上の方:158万円を超える
公的年金や私的年金などを含めた年金収入が基準を超える場合、源泉徴収されたうえで年金が支給されます。ただし、在職していない状況で年金を受給している方は、配偶者控除や扶養控除を適用させるための年末調整が行われません。
各種控除を受けられる方は翌年の確定申告を通じて税金の還付を受けられる可能性があるため、必要に応じて確定申告を行いましょう。なお、確定申告は必ずしも行う必要はなく、還付を受けられないことを承知で確定申告を省略しても問題ありません。
所得控除以上の年金を受給する場合、年金に対して課税されます。所得控除額や年金額は個人差があるため、いくらから課税されるかは一概にいえません。
公的年金だけでなく、私的年金も年金形式で受け取る場合は雑所得として取り扱われます。一時金で受け取る場合は、雑所得ではなく退職所得となる点に留意しましょう。
個人年金保険は、契約者と年金受取人次第では贈与税がかかります。年金受取開始後に年金受取人が亡くなり、遺族が年金を受け取る場合は相続税の対象となるなど、課税関係が複雑です。

企業年金制度がある企業に勤めている方やiDeCo、個人年金保険に加入している方は、受け取り方で課税の方法が異なる点に注意しましょう。
なお、損をしない退職金の受け取り方や退職所得の計算方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
参考:損しない退職金の受け取り方は?税金や一時金の仕組みもわかりやすく解説!
参考:退職金・年金をもらう前に確認しておきたい退職所得控除とは?
公的年金等控除の早見表
年金に係る税額を計算するうえで重要なのが、公的年金等控除です。公的年金等控除とは年金収入から控除される所得控除の一つで、年金を受給している方の年齢や収入金額によって以下のように異なります。
【65歳未満】
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間1,000万円以下) | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間1,000万円超~2,000万円) | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間2,000万円超) |
|---|---|---|---|
| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
| 130万円超 410万円未満 | 年金収入金額×0.25 +27万5,000円 | 年金収入金額×0.25 +17万5,000円 | 年金収入金額×0.25 +7万5,000円 |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金収入金額×0.15 +68万5,000円 | 年金収入金額×0.15 +58万5,000円 | 年金収入金額×0.15 +48万5,000円 |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金収入金額×0.05 +145万5,000円 | 年金収入金額×0.05 +135万5,000円 | 年金収入金額×0.05 +125万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
【65歳以上】
| 公的年金等の 収入金額 | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間1,000万円以下) | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間1,000万円超~2,000万円) | 公的年金等控除額 (年金以外の所得が 年間2,000万円超) |
|---|---|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
| 330万円超 410万円未満 | 年金収入金額×0.25 +27万5,000円 | 年金収入金額×0.25 +17万5,000円 | 年金収入金額×0.25 +7万5,000円 |
| 410万円以上 770万円未満 | 年金収入金額×0.15 +68万5,000円 | 年金収入金額×0.15 +58万5,000円 | 年金収入金額×0.15 +48万5,000円 |
| 770万円以上 1,000万円未満 | 年金収入金額×0.05 +145万5,000円 | 年金収入金額×0.05 +135万5,000円 | 年金収入金額×0.05 +125万5,000円 |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 | 185万5,000円 | 175万5,000円 |
雑所得は総合課税の対象となる所得の一つで、ほかの所得と合算して所得税額が決まります。年金受給者の税金について、具体的なケースに当てはめて考えてみましょう。
【条件】
- 70歳
- 年金収入:350万円(うち、公的年金200万円・私的年金150万円)
- 不動産所得(家賃収入から諸経費を差し引いた額):300万円
- 社会保険料:50万円
- 公的年金等控除:350万円×0.25+27万5,000円=115万円
- 基礎控除:48万円
以上の場合、まずは年金に係る税金と不動産所得に関わる税金を分けて計算します。
- 年金(雑所得):350万円-115万円=235万円
- 不動産所得:300万円
- 所得の合計:235万円+300万円=535万円
- 控除合計:社会保険料控除50万円+基礎控除48万円=98万円
- 課税所得:535万円ー98万円=437万円
課税所得は437万円となり、以下の速算表に当てはめると、所得税額は「(437万円×20%)427,500円=44万,6,500円」となります。住民税は「437万円×10%=43万7,000円」です。
| 課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円から1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
このように、年金所得以外にも所得がある場合は、それぞれの所得を含めて税額を計算します。
今回は年金所得と不動産所得の例でシミュレーションしましたが、給与所得や事業所得を得ている方も、同じような流れです。それぞれの課税所得を計算し、各種控除を差し引いたうえで速算表に当てはめて計算しましょう。
確定申告が必要な年金受給者はどんな人?
以下にいずれにも該当する方は、公的年金の収入に対する確定申告は原則として必要ありません。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である
- 公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(※)が20万円以下である
※給与所得や年金以外の雑所得、配当所得など
ただし、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を適用させ、所得税の還付を受けるためには確定申告が必要です。ただし、確定申告は必須ではないため、行いたい方だけ行えば問題ありません。
海外在住の日本非居住者は公的年金から課税される?
年金を受けている方が海外に転出する場合は「非居住者」となり、課税関係が「居住者」と異なります。居住者とは、国内に住所を有している方や現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を指しており、居住者以外の個人が「非居住者」として取り扱われます。
非居住者が得た「国内源泉所得」は、源泉徴収の対象です。年金は国内源泉所得の対象で、以下の計算式で算出した金額が源泉徴収されます。
{年金支給額–(5万円※×年金額に係る月数)}×20.42%
※(65歳以上の場合は9万5,000円)
受給している年金が老齢年金で、居住する国が日本と「年金の受け取りに関する租税条約」を締結している場合、所定の手続きをすれば所得税の免除を受けられます。
租税条約を締結している国は、2024年9月現在で73カ国あります。国によって必要な書類は異なりますが、該当する方は「租税条約に関する届出書」をはじめとした必要書類を日本年金機構に提出しましょう。
自己負担が一気に増す?年金211万円の壁とは
年金211万円の壁とは、年金収入のみで生活している65歳以上の夫婦二人世帯が、住民税非課税世帯になるかどうかの収入額です。単身世帯の場合は「年金155万円の壁」になります。
なお、年金受給者が住民税非課税世帯に該当するかどうかの基準は、住んでいる地域によって異なります。厚生労働省が設けている「級地区分」により、「1級地」「2級地」「3級地」ごとに基準が以下のように決まっています。
| 1級地 | 2級地 | 3級地 | |
|---|---|---|---|
| 二人以上世帯 | 211万円 | 203万円 | 193万円 |
| 単身世帯 | 155万円 | 152万円 | 148万円 |
住民税非課税世帯になると、文字通り住民税が課税されません。また、国民健康保険料や介護保険料などの負担が軽減されます。
まとめ
年金がいくらから課税されるかどうかは、人によって異なります。適用される公的年金等控除の金額に差があるだけでなく、社会保険料控除や生命保険料控除など、個別の事情に応じた各種控除を考慮する必要があるためです。
年金収入が控除額の合計を超える場合、課税所得を算出したうえで速算表に当てはめれば、税額を計算できます。年金受給開始後の生活設計をするうえで、手取りの年金額を計算することは重要です。
年金と一口にいっても、公的年金だけでなく私的年金も含めて考えなければなりません。企業年金制度がある勤務先に勤めている方やiDeCoを行っている方は、受給額の見込みだけでなく手取り額も把握しておきましょう。

金融系ライター
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じて、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。FP1級と社会保険労務士資格を活かして、多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に、これまで1,000記事以上の執筆実績あり。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
国民年金基金連合会
国民年金基金連合会は、国民年金法に基づき設立された公的な年金制度であり、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、自営業者など国民年金の第1号被保険者の老後の所得保障の役割を担うものです。 国民年金基金連合会は、転居や転職により基金の加入員資格を喪失した中途脱退者に対して、年金や遺族一時金の支給を行っています。また、平成14年からは確定拠出年金の個人型年金の実施主体として、規約の作成や掛け金の収納業務なども行っています。 退職等により加入していた企業型DCを脱退し、6ヶ月以上移管の手続きを行わなかった場合、国民年金基金連合会に自動的に移管されます。その場合、現金で保管されるため追加の積立や運用指図を行うことができず、さらに移管時と保管時に手数料がかかります。
GPIF
GPIFとはGovernment Pension Investment Fundの略で、日本の年金積立金管理運用独立行政法人のこと。預託された公的年金積立金の管理、運用を行っている。 年金保険料から集められた公的年金積立金は、厚生労働大臣の預託により、GPIFが信託銀行や投資顧問会社などの運用受託機関を通して国内外の債券市場や株式市場で運用し、運用収益とともに年金給付の原資としている。 公的年金という性質上、長期的に安全かつ効率的な観点が重視されますが、2014年度以降、運用改善の流れからリスク運用の比率が高まり、国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%という基本ポートフォリオが組まれてきた。2020年4月から5年間の第4期中期目標期間においては、各25%ずつに変更されている。
総合課税
納税者の所得を合算し、課税所得を計算する仕組みのことです。具体的には、個人の所得のうち利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の8種類(一部例外あり)が対象。 (申告分離課税) 総合課税のようにほかの所得と合算せず、他の所得と分離して所得税を計算する。 (源泉分離課税) 他の所得と分離する所得のうち、所得を支払う者が、納税者に代わって税金を徴収し納める課税方式。
住民税
住民税は、居住地の自治体(市区町村および都道府県)に納める地方税で、地域の行政サービスを賄うために使われます。住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されます。 所得割は、前年の所得に基づき一律の税率(多くの場合10%)で計算されます。一方、均等割は所得に関わらず一律の金額(全国基準では年額5,000円程度)を納める部分です。 住民税は、所得税のような累進課税ではなく比例課税が基本で、納税額は所得や扶養状況などにより異なります。また、住民税は原則として前年の所得に基づき計算されるため、納税は翌年度に行われます。これにより、地域社会の運営を支える重要な財源となっています。