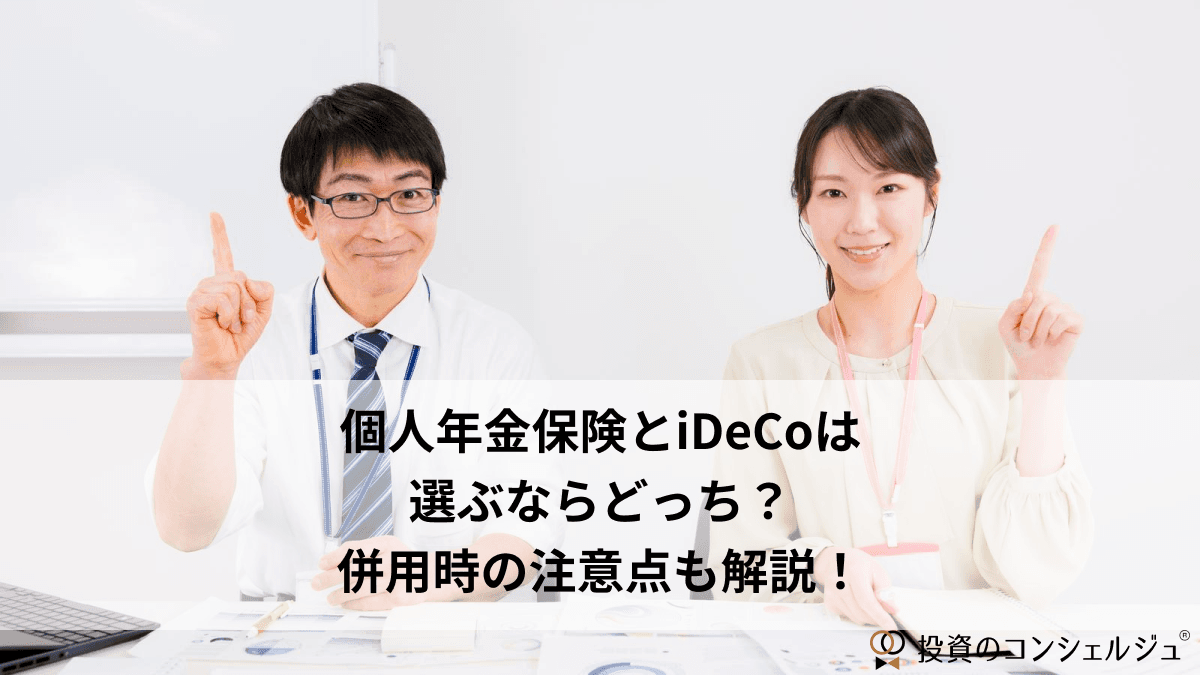個人年金保険よりも定期保険とiDeCoを組み合わせたほうが良いというのは本当ですか?
解決済み
0
2025/01/14 17:19
男性
40代
老後の備えとして個人年金保険への加入を検討しています。掛け捨て保険と比べて保障の機能もあり、将来年金にもなるのでお得だなと感じています。しかし、知人に相談したところ、個人年金保険は割に合わないから、必要な定期保険に加入したうえでiDeCoを活用して資産運用したほうがいい、といわれました。 本当にそうなのでしょうか?どのようなポイントで比較検討すればいいか教えて下さい。
回答
株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長
個人年金保険の選択には慎重な検討が必要です。知人のアドバイスには一理あり、純粋な投資効率に加えて、税制優遇措置の観点からも、個人年金保険よりもiDeCoを活用した資産運用のほうが有利な場合が多いといえます。
また、個人年金保険の保障機能は、「万一の場合、払込保険料相当額の死亡給付金を受け取れる」というものであり、iDeCoの場合も「死亡一時金」として受け取ることができるので特に個人年金保険の保障が優れているというわけではありません。
税制優遇措置を比較してみましょう。個人年金保険の場合、支払った保険料が「個人年金保険料控除」として、年間最大8万円まで所得控除の対象となります。個人年金保険料控除には上限額があり、所得税と住民税で控除額が異なるという複雑さがあります。
一方、iDeCoは掛金の全額が所得控除の対象となり、運用益も非課税です。さらに受取時にも退職所得控除や公的年金等控除が適用さます。また、2024年から恒久化された新NISAでは、年間で最大360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)の投資が可能で、その運用益が非課税となります。
このような税制面での違いに加え、個人年金保険には運用面での課題もあります。現在の予定利率は1%にも満たないケースが多く、例えば住友生命の場合、2024年9月時点で0.8%となっています。これに対し、iDeCoであれば、インデックスファンド等の安定性の比較的高い商品へのドルコスト平均法による投資で、長期的にはより高いリターンを期待することができます。
定期保険も生命保険料控除の対象となるため、iDeCo+定期保険であれば、iDeCoの掛け金全額と、定期保険の保険料が所得控除の対象となります。
個人年金保険もiDeCoも半強制的に積立運用を行うことになるため、自己管理でコツコツ運用することが苦手な人でも資産運用が可能となるメリットは共通です。大きな違いは、iDeCoは引き出しが60歳までできない反面、個人年金保険は元本割れさえ気にしなければ解約し現金化することは比較的容易という点です。
中途引き出しが原則的にできない、という点さえ許容できれば、知人の方のご指摘通り、必要な保障は定期保険で確保し、資産形成はiDeCoやNISAを活用する方が税制優遇措置の面でも投資効率の面でも合理的です。もし資金の状況と生命保険料控除にゆとりがある場合、iDeCo等確定拠出年金と個人年金保険を組み合わせることで、より安定的な資産形成が可能になる可能性もあります。
保険の機能と投資効率、税制優遇措置、そして何より自身の特性や価値観を総合的に判断して、決定することをお勧めします。もしお悩みの場合は、専門家までぜひご相談下さい。
関連記事
関連質問
関連する専門用語
個人年金保険
個人年金保険とは、公的年金だけでは不足しがちな老後資金を、自助努力で補うために設計された私的年金商品です。契約者が決められた期間にわたり保険料を払い込み、あらかじめ設定した開始年齢(60歳・65歳など)に達すると年金形式で受け取りが始まります。受取方法には、決められた年数だけ確実に受け取る「確定年金型」と、生存している限り終身で受け取れる「終身年金型」があり、どちらを選ぶかによって総受取額や万一の際の遺族保障の形が異なります。変額型や外貨建て型など、インフレ対応や為替分散を意識したバリエーションも登場しています。 大きな魅力の一つは税制優遇です。一定の要件(受取人が契約者本人または配偶者、払込期間が10年以上など)を満たす契約であれば、払込保険料は「個人年金保険料控除」として所得控除の対象になります。たとえば年間保険料が8万円の場合、所得税で最大4万円、住民税で最大2万8千円が控除され、課税所得を圧縮できるため実質負担を抑えながら老後資金を積み立てられる点がメリットです。 一方で注意すべき点もあります。途中解約時には元本割れが生じやすく、解約返戻金が払込総額を下回るケースが多いこと、固定利率型の商品ではインフレに追いつけない可能性があること、そして保険会社が破綻した場合でも保険契約者保護機構による補償は責任準備金の90%が上限となることです。また、税優遇制度としては個人型確定拠出年金(iDeCo)や新NISAも利用できるため、流動性・運用商品の自由度・掛金上限などを比較し、自分に合った組み合わせを検討する必要があります。 これらの特徴を踏まえると、個人年金保険は「計画的に積立を続け、税制メリットを生かしながら老後の生活費を補完したい」人に適した選択肢といえます。生活防衛資金や他の運用枠を確保したうえで長期的な資産形成の一環として活用すれば、老後のキャッシュフローに安定感をもたらす手段となるでしょう。
iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金の愛称で、老後の資金を作るための私的年金制度です。20歳以上65歳未満の人が加入でき、掛け金は65歳まで拠出可能。60歳まで原則引き出せません。 加入者は毎月の掛け金を決めて積み立て、選んだ金融商品で長期運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取ります。加入には金融機関選択、口座開設、申込書類提出などの手続きが必要です。 投資信託や定期預金、生命保険などの金融商品で運用し、税制優遇を受けられます。積立時は掛金が全額所得控除の対象となり、運用時は運用益が非課税、受取時も一定額が非課税になるなどのメリットがあります。 一方で、証券口座と異なり各種手数料がかかること、途中引き出しが原則できない、というデメリットもあります。